サッカーの試合が、手に汗握る延長戦の末に同点…そんなとき、勝敗を決めるために行われるのが「PK戦」です。一人のキッカーと一人のゴールキーパー、ゴールまでわずか11mの距離で繰り広げられる一対一の真剣勝負は、観る者の心を鷲掴みにします。
ワールドカップなどの大舞台では、このPK戦によって数々のドラマが生まれてきました。しかし、その一方で「試合中に行われるPKと何が違うの?」「サドンデスってどういう意味?」「細かいルールがよくわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、そんなPK戦の基本的なルールから、知っているとさらに観戦が楽しくなる豆知識まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説していきます。
PK戦とは?基本的なルールを徹底解説

サッカーの試合を最後まで見ていると、時折「PK戦」という言葉を耳にします。これは試合の勝敗を決めるための特別な方法ですが、一体どのようなルールで行われているのでしょうか。ここでは、PK戦の基本的な定義や行われる条件、そして試合中に発生する「ペナルティーキック(PK)」との違いについて、わかりやすく解説します。
そもそもPK戦ってどんなもの?
PK戦とは、サッカーの試合で規定の試合時間(前後半90分)と、大会によっては延長戦(前後半30分)を行っても勝敗が決まらない場合(同点の場合)に、勝者を決めるために行われるタイブレーク方式の一つです。 正式名称は「ペナルティーシュートアウト」と言います。
ただし、PK戦で勝敗が決まった場合でも、公式記録上、その試合結果は「引き分け」として扱われます。 あくまでも、トーナメント戦などで次のステージに進むチームを決めるための便宜的な方法という位置づけなのです。
PK戦が行われる条件とは?
PK戦は、どのような試合でも行われるわけではありません。 主に、トーナメント方式の大会のように、必ず勝敗を決めなければならない試合で採用されます。
具体的な例としては、以下のような大会が挙げられます。
- FIFAワールドカップの決勝トーナメント
- 天皇杯や高校サッカー選手権などの国内カップ戦
これらの大会では、90分間で決着がつかない場合、まず延長戦が行われます。それでも同点の場合はPK戦に突入し、勝者を決定します。
一方で、Jリーグなどのリーグ戦では、引き分けでも勝点が与えられるため、基本的にPK戦は行われません。 昔のJリーグでは引き分けがなく、延長戦やPK戦で必ず勝敗を決めていた時代もありましたが、現在は国際基準に合わせて引き分け制度が採用されています。
PK(ペナルティーキック)との違いは?
PK戦と混同されやすいのが、試合中に行われる「ペナルティーキック(PK)」です。 この二つは、ボールを蹴る場所や状況が似ているため同じものと思われがちですが、発生する条件とルールに明確な違いがあります。
ペナルティーキック(PK)は、守備側のチームが自陣のペナルティーエリア内で、直接フリーキックに相当する反則を犯した場合に、攻撃側のチームに与えられます。 これは試合の流れの中で発生するプレーの一つであり、得点のチャンスとなります。
| PK戦 | ペナルティーキック(PK) | |
|---|---|---|
| 目的 | 試合の勝敗を決めるため | 反則に対する罰則、得点の機会 |
| タイミング | 延長戦を含め試合が終了し、同点の場合 | 試合時間中 |
| キッカーの数 | 両チーム5人ずつ(決着がつかなければそれ以上) | 1人 |
| キック後のプレー | 一度蹴ったボールに再び触れることはできない | GKが弾いたボールなどを他の選手や自分が詰めてゴールを狙える |
最も大きな違いは、キック後のプレーが続くかどうかです。 試合中のPKでは、ゴールキーパーが弾いたボールや、ゴールポストに当たって跳ね返ったボールを、他の選手や蹴った本人もプレーに絡んでゴールを狙うことができます。 しかし、PK戦ではキッカーがボールに触れるのは一度きりで、跳ね返ったボールに触れることはできず、その時点でキックは終了となります。 このように、PKとPK戦は似て非なるものなのです。
PK戦の詳しい流れと手順

PK戦は、試合終了のホイッスルが鳴った直後から、独特の緊張感の中で進行していきます。ここでは、主審によるコイントスから始まり、キッカーたちがどのような流れでシュートを打ち、勝敗が決まるのか、その詳細な手順を順を追って見ていきましょう。
コイントスからキッカーの順番決定まで
PK戦は、試合終了後、主審が両チームのキャプテンを呼び寄せることから始まります。 ここで2回のコイントスが行われ、PK戦の舞台設定が決められます。
- 使用するゴールの決定: 最初のコイントスで、PK戦を行うゴールをどちらにするか決定します。 これは主審が行い、ピッチの状態や安全性などを考慮して主審が決定することもあります。
- 先攻・後攻の決定: 2回目のコイントスで勝ったチームが、先に蹴るか(先攻)、後に蹴るか(後攻)を選択する権利を得ます。 先に蹴る方が精神的に有利とされるデータもあり、多くのチームが先攻を選びます。
これらの決定が終わると、各チームはPK戦に参加する選手(キッカー)の順番を決めます。 順番は監督や選手たち自身で決定し、主審に事前に申告する必要はありません。 キッカー以外の選手は、センターサークル内で待機することになります。
5人ずつ蹴るのが基本!勝敗の決まり方
PK戦の基本的な形式は、両チーム5人ずつが交互にキックを行うというものです。 先攻チームの1人目が蹴り、次に後攻チームの1人目が蹴る、という流れで5人目まで続きます。
勝敗は、5人全員が蹴り終わった時点でのゴール数で決まります。より多くゴールを決めたチームの勝利です。
ただし、5人全員が蹴る前に勝敗が決まるケースもあります。例えば、3人ずつ蹴り終わった時点でスコアが3-0となり、まだ蹴っていない2人が全員ゴールを決めたとしても追いつけない場合など、一方のチームの勝利が確定した時点でPK戦は終了します。
6人目以降のサドンデス方式とは?
5人ずつが蹴り終わっても両チームのスコアが同じだった場合、PK戦は6人目以降に突入します。 ここからは「サドンデス方式」と呼ばれるルールが適用されます。
サドンデス方式とは、両チームが1人ずつキックを続け、どちらかのチームが成功し、もう一方のチームが失敗するなど、スコアに差がついた時点で勝敗が決まる方式です。 例えば、先攻の6人目が成功し、後攻の6人目が失敗すれば、その時点で先攻チームの勝利となります。 もし両者成功、あるいは両者失敗した場合は、7人目、8人目…と決着がつくまで続いていきます。
このサドンデス方式は、1本のキックの重みがさらに増し、見ている側も息をのむような緊張感に包まれます。
ABBA方式とは?現在はどうなってる?
PK戦の公平性を高める目的で、過去に「ABBA方式」という新しい形式が試験的に導入されたことがあります。
従来の方式(ABAB方式)では、常に先行チームがリードする可能性があるため、後攻チームに精神的なプレッシャーがかかりやすく、先行が有利というデータがありました。
これに対しABBA方式は、テニスのタイブレークのように、 Aチーム → Bチーム → Bチーム → Aチーム → Aチーム… という順番で蹴ることで、後攻のプレッシャーを軽減し、公平性を保つことを目指したものです。
この方式はU-20ワールドカップや日本の天皇杯などで試されましたが、手順が複雑であることなどを理由に、現在は正式採用には至っておらず、議論も打ち切られています。 そのため、現在の主要な大会では、従来通りの交互に蹴る方式が採用されています。
PK戦をめぐる細かいルールと疑問

PK戦には、基本的な流れ以外にも、選手の資格やゴールキーパーの動き、ボールの扱いなど、様々な細かいルールが存在します。ここでは、PK戦を観戦する上で生じるであろう疑問に答えながら、より深くルールを掘り下げていきます。
キッカーになれる選手・なれない選手
PK戦のキッカーは誰でも務められるわけではありません。原則として、試合終了のホイッスルが鳴った時点でピッチ上にいた選手のみが、PK戦に参加する資格を持ちます。 試合中に交代してベンチに下がった選手や、退場処分を受けた選手は参加できません。
また、試合終了時にどちらかのチームが退場者を出して人数が少なくなっていた場合、人数の多い方のチームは、少ない方のチームと同じ人数になるように選手を除外しなければなりません。 例えば、Aチームが11人、Bチームが10人で試合を終えた場合、Aチームは1人を除外して10人でPK戦に臨みます。 除外された選手はPK戦には参加できません。
ゴールキーパーのルール(反則と再キック)
PK戦の主役の一人であるゴールキーパーにも、厳格なルールが定められています。
もしゴールキーパーがボールを蹴られる前にゴールラインから前に出てしまい、その結果ゴールが防がれた場合、そのキックはやり直し(再キック)となります。 ゴールキーパーの反則が繰り返されると、警告(イエローカード)が出されることもあります。
さらに、ゴールポストやクロスバーを揺らしたり、キッカーを過度に挑発したりするようなリスペクトに欠ける行為も禁止されています。
蹴ったボールがポストやバーに当たったら?
PK戦では、キッカーが蹴ったボールの行方についても明確なルールがあります。
試合中のPKとは異なり、PK戦ではキッカーは一度ボールを蹴った後、再びボールに触れることはできません。 これは、蹴ったボールがゴールポストやクロスバーに当たって跳ね返ってきた場合も同様です。 跳ね返ったボールを再び蹴ってゴールに入れても得点にはなりません。
ボールがゴールキーパーにセーブされて跳ね返ってきた場合も同じで、その時点でそのキッカーのプレーは終了となります。
ただし、ボールがゴールキーパーやポストに当たった後、その勢いでゴールラインを越えた場合は得点として認められます。 主審は、ボールの動きが完全に止まるまでプレーを見届ける必要があります。
2周目に突入したらキッカーの順番は?
サドンデス方式でも決着がつかず、両チームのフィールドプレーヤーとゴールキーパーを合わせた11人全員が蹴り終えても同点だった場合、PK戦は2巡目に突入します。
この場合もサドンデス方式は継続されますが、キッカーの順番については、1巡目と同じ順番で蹴る必要はありません。 チームは自由に2巡目のキッカーの順番を決めることができます。
一度キッカーを務めた選手は、自分のチームの参加資格のある選手全員が蹴り終わるまでは、2回目のキッカーになることはできません。 非常に稀なケースですが、2巡目、3巡目と続く壮絶なPK戦になる可能性もルール上は存在します。
PK戦の歴史と記憶に残る名勝負
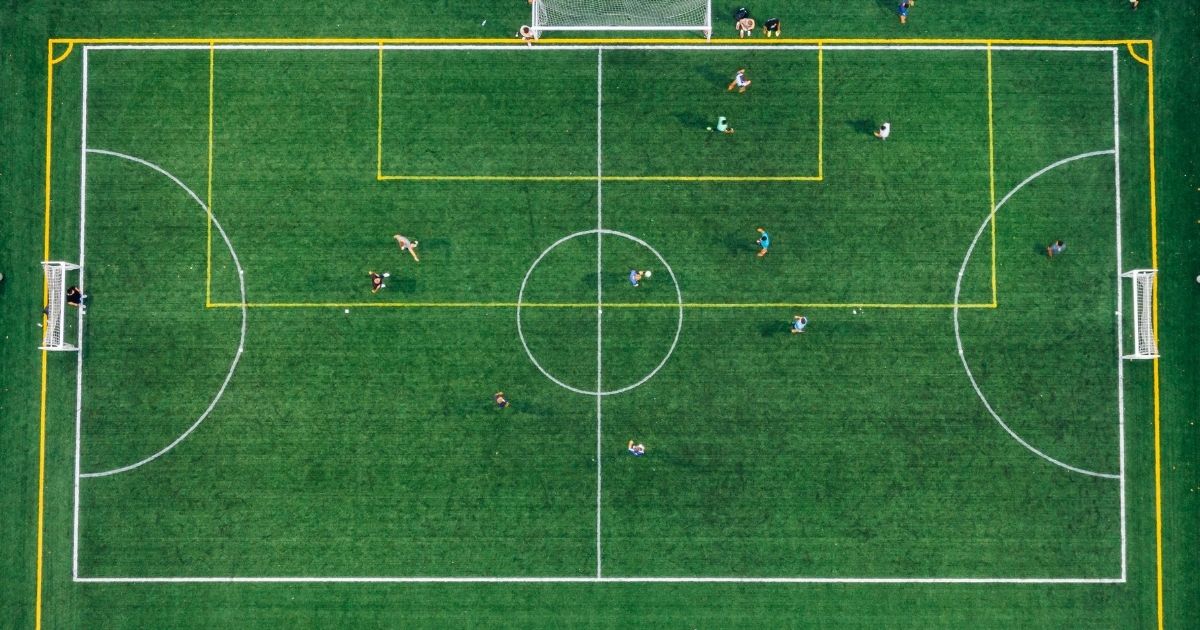
今やサッカーの勝敗を決する上で欠かせない存在となったPK戦ですが、その歴史は意外にも新しいものです。ここでは、PK戦がいつ、どのような背景で導入されたのか、そしてワールドカップなどの大舞台で繰り広げられた伝説的な名勝負を振り返ります。
PK戦はいつから導入された?その背景
PK戦がサッカーの公式ルールとして導入されたのは、1970年のことです。 比較的最近のルールと言えるでしょう。それ以前は、トーナメント戦で引き分けとなった場合、勝敗を決めるために様々な方法が取られていました。
- 再試合: 日程を改めて、もう一度試合を行っていました。
- 抽選(コイントスなど): 試合内容とは全く関係のない、純粋な運で勝敗を決めていました。
しかし、再試合は選手たちの体力的な負担が大きく、大会の日程も過密になります。 また、コイントスによる決着は、あまりにも残酷でスポーツマンシップに欠けるという批判がありました。
こうした問題点を解決するために、選手の技術と精神力が試される、よりサッカーらしい決着方法としてPK戦が考案され、導入されるに至ったのです。
ワールドカップ史に残る伝説のPK戦
ワールドカップという最高峰の舞台では、PK戦が数々のドラマを生み出してきました。その中でも特に人々の記憶に刻まれているのが、1994年アメリカワールドカップ決勝のブラジル対イタリアのPK戦です。
0-0のまま120分の死闘を終え、ワールドカップ史上初めて決勝戦がPK戦にもつれ込みました。 注目が集まったのは、イタリアの至宝、ロベルト・バッジョでした。大会を通してイタリアを牽引してきたスーパースターでしたが、5人目のキッカーとして登場した彼のシュートは、無情にもクロスバーの上へと大きく外れてしまいます。 この瞬間、ブラジルの4度目の優勝が決まり、ピッチに崩れ落ちるバッジョの後ろ姿は「バッジョの悲劇」として世界中のサッカーファンの心に深く刻まれました。
また、2022年カタールワールドカップでは、日本代表が決勝トーナメント1回戦でクロアチア代表と対戦し、PK戦の末に惜しくも敗退しました。 この試合も、PK戦の残酷さとドラマ性を改めて多くの人に印象付けた一戦と言えるでしょう。
Jリーグや国内大会での有名なPK戦
日本国内の大会においても、PK戦は数々の名場面を演出してきました。
例えば、2000年シドニーオリンピックの準々決勝、日本対アメリカの試合は、多くのファンの記憶に残っています。 当時「史上最強」との呼び声も高かった日本代表は、2-2の末にPK戦に突入。しかし、中田英寿選手や中村俊輔選手といった中心選手が次々と失敗し、メダル獲得の夢を絶たれてしまいました。
また、天皇杯や全国高校サッカー選手権など、一発勝負のトーナメントでは毎年のようにPK戦での熱闘が繰り広げられています。特に高校サッカーでは、選手たちの懸命なプレーと、勝者と敗者のコントラストが、観る者に大きな感動を与えています。これらの試合は、PK戦が単なる運試しではなく、チームの総合力が問われる真剣勝負であることを示しています。
まとめ:PK戦とは、サッカーの魅力を凝縮した勝負の形

この記事では、サッカーのPK戦について、その基本的なルールから歴史、そして記憶に残る名勝負までを詳しく解説してきました。
PK戦は、延長戦でも決着がつかない場合に、両チーム5人ずつのキッカーがゴールから11mの距離からシュートを放ち、勝敗を決める方法です。 試合中のペナルティーキックとは異なり、一度蹴ったボールに再び触れることはできません。 5人で決着がつかなければ、1本ずつ勝敗が決まるサドンデス方式に突入します。
このシンプルなルールの中に、キッカーの技術、ゴールキーパーの読み、そして極限のプレッシャーに打ち勝つ精神力といった、サッカーの持つ様々な要素が凝縮されています。 それは単なる運試しではなく、選手たちの力量が試される、もう一つの真剣勝負なのです。
PK戦のルールを知ることで、サッカー観戦がさらに奥深く、エキサイティングなものになるはずです。次にPK戦を見る機会があれば、ぜひこの記事で得た知識を思い出しながら、選手たちの繰り広げる究極のドラマを堪能してください。



