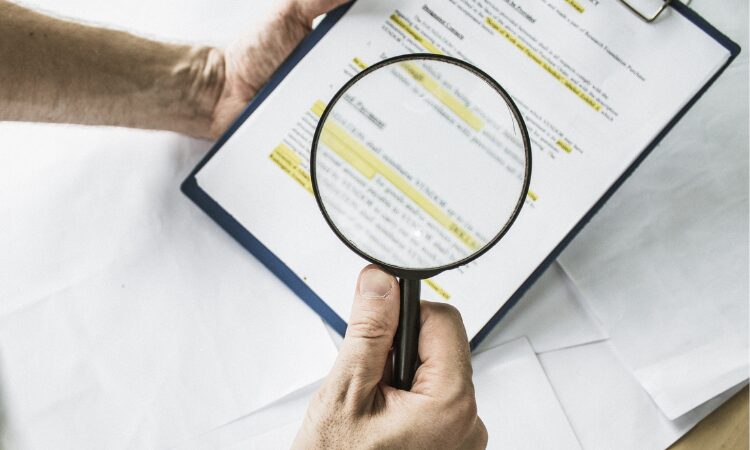世界最高峰のサッカーリーグ、イングランド・プレミアリーグ。きらびやかな舞台の裏側で、選手たちが乗り越えなければならない非常に厳しい「壁」があることをご存知でしょうか。それが、イギリスの労働許可証の存在です。特に2021年のブレグジット(イギリスのEU離脱)以降、そのルールはさらに厳格化され、これまで自由に移籍できていたEU国籍の選手でさえも、この許可証が必要になりました。
「なぜプレミアリーグでプレーするには許可証がいるの?」「どんな条件をクリアすればいいの?」そんな疑問を抱くサッカーファンは少なくありません。この記事では、プレミアリーグの労働許可証を取得するための「GBE」という制度の仕組みや、具体的な条件、そして日本人選手たちがどのようにしてこの高いハードルを越えてきたのかを、誰にでもわかるようにやさしく解説していきます。
プレミアリーグの労働許可証の厳しい条件とは?

世界中のトッププレイヤーが集まるプレミアリーグでプレーするためには、サッカーの実力だけでなく、イギリス政府が定める厳格な基準をクリアし、労働許可を得る必要があります。この項目では、その許可証の正体と、なぜこれほどまでに条件が厳しいのか、その背景に迫ります。
イギリスでプレーするために必要な「GBE」とは?
これがいわゆる「労働許可証」の実体であり、これを得られて初めて、イギリスの就労ビザを申請する資格が生まれます。
このGBE制度は、2021年にイギリスがEUから離脱したタイミングで、ルールが新しくなりました。それまではEU国籍の選手であれば、比較的自由にイギリス国内のクラブと契約できましたが、ブレグジット後はEU国籍の選手もその他の外国籍選手と同じ土俵で審査されることになったのです。
この制度の最大の特徴はポイント制であることです。選手の過去の実績を客観的な数値に置き換え、合計ポイントが基準に達しているかどうかでGBEを発行するかどうかを判断します。具体的には、A代表での出場歴、所属クラブのリーグレベルや国内外の大会での出場時間・成績など、多岐にわたる項目で評価されます。このポイントが一定基準(原則15ポイント)に達すれば自動的にGBEが発行され、プレミアリーグへの道が開かれますが、そうでなければ原則として移籍は認められません。
なぜ労働許可証はこんなに厳しいのか?その背景
プレミアリーグの労働許可証の条件がこれほど厳しいのには、明確な理由があります。その最も大きな目的は「自国(イングランド)選手の育成と出場機会の確保」です。
世界中からスター選手が集まるプレミアリーグは、非常に高い人気と莫大な放映権料を誇ります。そのため、各クラブは潤沢な資金力を背景に、世界中から即戦力となる優秀な選手を獲得しようとします。もし何の規制もなければ、チームの登録選手がほとんど外国籍選手で占められてしまう可能性もゼロではありません。
そうなると、イングランド国内の若手選手がトップチームでプレーする機会が失われ、将来のイングランド代表チームの弱体化に繋がるのではないか、という懸念が生まれます。そこでFA(イングランドサッカー協会)は、労働許可証という形で外国籍選手の流入に一定のフィルターをかけることで、国内選手の成長を促し、イングランドサッカー界全体のレベルを維持・向上させることを目指しているのです。
また、単に選手の実力を測るだけでなく、「イギリスのサッカー界に貢献できる、本当に質の高い選手か」を見極めるという側面もあります。厳しい基準を設けることで、リーグ全体の質の高さを担保し、「世界最高峰」というブランドイメージを守ることにも繋がっているのです。
ブレグジット(イギリスのEU離脱)による大きな変化
2020年12月31日をもって完了したイギリスのEU離脱、通称「ブレグジット」は、プレミアリーグの移籍市場に大きな地殻変動をもたらしました。それまで、イギリスはEU加盟国だったため、「労働移動の自由」という原則のもと、EU加盟国のパスポートを持つ選手は労働許可証なしで自由にプレミアリーグのクラブと契約し、プレーすることが可能でした。
しかし、ブレグジットによってこの特例はなくなりました。フランス、スペイン、ドイツ、ベルギーといったEU加盟国の選手たちも、日本人選手やブラジル人選手などと全く同じように、GBEのポイント基準を満たさなければならなくなったのです。これにより、プレミアリーグのクラブは、これまでのように若くて才能あるEU域内の選手を安価で獲得し、育成するという戦略が取りにくくなりました。
この変化は、スカウト戦略にも大きな影響を与えています。EU内外を問わず、全ての外国籍選手を同じ基準で評価する必要があるため、より実績があり、GBEのポイントを確実にクリアできる選手の獲得が重視される傾向が強まりました。例えば、A代表でのキャップ数(試合出場数)が少ない若手選手よりも、代表や所属クラブでコンスタントに試合に出場し、確かな実績を積み重ねている選手の方が、移籍市場での価値が高まることになります。この厳格化は、プレミアリーグへの移籍のハードルを全体的に引き上げる結果となりました。
GBE取得の2つのルート:自動発給と例外パネル

プレミアリーグでプレーするための推薦状「GBE」を取得するには、大きく分けて2つの方法があります。一つは定められたポイントをクリアして自動的に発給されるルート、もう一つはポイントが足りなくても特別な審査を経て認められるルートです。ここでは、その2つのルートについて詳しく見ていきましょう。
ルート1:自動発給基準をクリアする(15ポイント以上)
GBEを取得するための最も確実でストレートな方法は、FAが定めるポイント計算で合計15ポイント以上を獲得することです。この基準をクリアした選手は、「プレミアリーグでプレーするに足る実力と実績がある」と客観的に判断され、自動的にGBEが発行されます。
ポイントは、主に以下の6つのカテゴリー(テーブル)で評価され、それぞれの実績に応じて加算されていきます。
- A代表での出場割合
- 国内リーグでの出場時間の割合
- クラブでの大陸選手権(UEFAチャンピオンズリーグなど)での出場時間の割合
- 前所属クラブの最終リーグ順位
- 前所属クラブの大陸選手権での成績
- 移籍元リーグのレベル(質)
これらの項目は、選手の直近12ヶ月(または24ヶ月)の実績に基づいて評価されます。つまり、コンスタントに高いレベルでプレーし続けていることが、15ポイントという高いハードルを越えるための絶対条件となります。特に、自国のA代表に選ばれ、公式戦に出場している実績は非常に重要視されます。FIFAランキング上位国の代表選手であれば、一定の出場割合を満たすだけで自動的に労働許可が下りるケースもあります。この自動発給基準をクリアすることが、全ての選手にとっての第一目標となります。
ポイントはどのように計算される?具体的な内訳を解説
GBEの15ポイントが、具体的にどのように計算されるのか、その内訳を見ていきましょう。評価項目は多岐にわたり、それぞれが選手の「質」を測るための指標となっています。
基本的には、「代表での活躍」と「クラブでの活躍」の2つの側面から評価されます。
| 評価カテゴリー | 主な内容 |
|---|---|
| テーブル1:代表での出場 | 過去24ヶ月間のA代表公式戦での出場時間割合。国のFIFAランキングによって、必要な出場割合や獲得ポイントが変わる。 |
| テーブル2:国内リーグでの出場 | 過去12ヶ月間の国内リーグでの総出場時間に対する出場割合。 |
| テーブル3:大陸選手権での出場 | 過去12ヶ月間の大陸選手権(CL, EL, ACLなど)での総出場時間に対する出場割合。 |
| テーブル4:クラブのリーグ成績 | 前所属クラブの国内リーグ最終順位。リーグを制覇したり、大陸選手権出場権を獲得したりすると高ポイント。 |
| テーブル5:クラブの大陸選手権成績 | 前所属クラブが大陸選手権でどこまで勝ち進んだか。グループステージ突破や優勝でポイントが加算。 |
| テーブル6:移籍元リーグの質 | 移籍元のリーグがどのレベルに格付けされているか(Band 1〜6)。 |
プレミアリーグやラ・リーガなどの欧州トップリーグは「Band 1」に分類され、そこでプレーしているだけで高いポイントが得られます。一方で、Jリーグは以前Band 6に分類されていましたが、近年評価が見直され、現在はBand 4〜6の範囲に含まれています。
例えば、Jリーグ(仮にBand 4とする)のクラブで90%以上の試合に出場し、クラブがリーグ優勝を果たし、ACLでも活躍し、さらに日本代表でも多くの試合に出ている、といった複数の条件を高いレベルで満たして、ようやく15ポイントに近づくことができます。このように、複数の項目で高い実績を積み上げることが不可欠なのです。
ルート2:例外パネル(ESC)による審査
合計ポイントが15点に届かなかった場合でも、プレミアリーグへの道が完全に閉ざされるわけではありません。合計10〜14ポイントの選手には、「例外パネル(Exceptions Panel)」という、いわば“敗者復活”のチャンスが与えられます。
このパネルは、サッカー界の専門家や元選手などで構成される独立した審査会です。ポイントという数字だけでは測れない選手の将来性や、移籍がプレミアリーグに与えるポジティブな影響などを総合的に判断し、GBE発給の是非を決定します。
例えば、「まだ若いが、同世代の選手の中で突出した才能を持っている」「移籍金が非常に高額で、それだけ市場価値が認められている」「給与がチーム内でトップクラスであり、クラブからの期待の高さを示している」といった点が考慮されます。
ただし、この例外パネルを要求できるのは、あくまで10ポイント以上を獲得している選手に限られます(ユース選手などの例外を除く)。9ポイント以下の選手はこの審査を受けることすらできません。例外パネルはあくまで救済措置であり、非常に狭き門であることに変わりはありません。それでも、三笘薫選手や冨安健洋選手のように、この制度を利用してプレミアリーグ移籍を実現したとされるケースもあります。
【具体例】日本人選手はどのように条件をクリアした?

厳しい労働許可証の条件を、日本人選手たちはどのように乗り越えてきたのでしょうか。ここでは、プレミアリーグで活躍する代表的な選手を例に、彼らが歩んだ道のりを具体的に見ていきます。彼らの移籍の裏側には、緻密な戦略と確かな実績の積み重ねがありました。
三笘薫選手の場合:代表実績と移籍戦略
ブライトンで圧倒的なドリブル突破を武器に活躍する三笘薫選手。彼がJリーグの川崎フロンターレから移籍した際、労働許可証の取得は大きな注目を集めました。
三笘選手の場合、Jリーグでの活躍は目覚ましいものがありましたが、移籍当時はA代表での出場経験がまだ浅かったため、自動発給基準である15ポイントを満たすのは難しい状況でした。Jリーグは当時、リーグレベルの評価(Band)が低く、国内での実績だけではポイントを稼ぎにくいという事情もありました。
そこで、ブライトンは戦略的なアプローチを取りました。まず三笘選手と契約を結び、労働許可証の基準が比較的緩やかなベルギーリーグのユニオン・サン=ジロワーズへ1年間レンタル移籍させたのです。ベルギーリーグはJリーグよりも高い「Band 2」にランク付けされており、そこで主力としてプレーし、結果を残すことでGBEポイントを積み増す狙いがありました。
さらに、このレンタル期間中に日本代表での出場機会を増やし、キャップ数を着実に重ねていきました。ベルギーでの活躍と代表での実績、この2つを積み上げたことで、最終的に労働許可証の基準をクリアし、プレミアリーグの舞台に立つことができたのです。例外パネル(ESC)での審査を経て認められた可能性も指摘されており、彼の才能が高く評価された結果と言えるでしょう。
遠藤航選手の場合:ドイツでの実績と代表キャップ数
リヴァプールという世界的なビッグクラブへ電撃移籍し、中盤の要として活躍する遠藤航選手。彼の移籍は、GBE制度において「継続的な実績」がいかに重要かを示す好例です。
遠藤選手は、プレミアリーグに移籍する直前まで、ドイツ・ブンデスリーガのVfBシュトゥットガルトでキャプテンを務めていました。ブンデスリーガは、プレミアリーグと同じく世界最高峰のリーグ「Band 1」に分類されています。そこで長年にわたりレギュラーとしてプレーし、デュエル(1対1の強さ)王として名を馳せた実績は、GBEポイントにおいて非常に高く評価されました。
さらに、遠藤選手は日本代表のキャプテンも務めており、豊富な国際Aマッチ出場経験を持っています。FIFAランキングで20位前後につける日本代表で、長期間にわたって主力であり続けたことは、代表関連のポイントで大きなアドバンテージとなりました。
このように、
- レベルの高いリーグ(Band 1)での豊富な出場実績
- 代表チームでの長年にわたる貢献とキャプテンシー
という2つの強力な要素を兼ね備えていたことで、遠藤選手はGBEのポイント基準を問題なくクリアできたと考えられます。Jリーグから直接ではなく、一度欧州の主要リーグを経由してステップアップしたことが、世界最高峰の舞台への扉を開くことにつながりました。
冨安健洋選手の場合:セリエAでの活躍が評価
アーセナルでディフェンスラインの様々なポジションをこなし、高い評価を得ている冨安健洋選手。彼もまた、欧州の主要リーグでのステップアップを経てプレミアリーグ移籍を実現した選手の一人です。
冨安選手は、Jリーグのアビスパ福岡からベルギーのシント=トロイデンVVへ移籍し、そこでの活躍が認められてイタリア・セリエAのボローニャFCへとステップアップしました。セリエAもブンデスリーガ同様、リーグレベルの評価が最も高い「Band 1」に分類されています。
ボローニャで2シーズンにわたり、若くして不動のレギュラーとしてプレーし、対人守備の強さや戦術理解度の高さを証明しました。このトップリーグでの確固たる実績が、GBEポイントを稼ぐ上で大きな基盤となりました。
また、若い頃から各年代別の日本代表に選出され、A代表でもレギュラーとして定着していたことも重要な要素です。アーセナルへの移籍は高額な移籍金も伴っており、市場価値の高さも証明していました。これらの要素から、冨安選手は例外パネル(ESC)での審査を経て労働許可証が発行された可能性が高いと見られています。彼のケースは、若手であってもトップリーグで主軸として活躍すれば、プレミアリーグへの道が開かれることを示しています。
若手選手や例外的なケースはどうなる?

これまで見てきたように、プレミアリーグの労働許可証はA代表やトップチームでの実績が大きく影響します。では、まだ実績の少ない若手選手や、女子サッカー、あるいは監督やスタッフの場合はどうなるのでしょうか。ここからは、そうした少し特殊なケースについて解説します。
期待の若手選手向けの特例措置
A代表での出場経験がなく、トップチームでの出場時間も少ない18歳から21歳くらいの若手有望株にとって、15ポイントの壁は非常に高いものです。しかし、FAは将来有望な才能を無下にしないための特例措置を設けています。
GBEのポイントシステムには、ユース選手向けの評価項目が存在します。例えば、U-21などの年代別代表での公式戦出場歴や、所属クラブのユースチームでの大会出場歴などもポイント加算の対象となる場合があります。これにより、A代表歴がない選手でも、ユース年代で国際的な実績があれば、ポイントを獲得する道が残されています。
さらに、2023年のルール改定では、クラブごとに労働許可証の基準を満たさない選手を獲得できる「資格外選手枠」というものが導入されました。これは、イングランド人選手の出場時間が多いクラブほど多くの枠(最大4枠)を与えられるというもので、クラブが将来性を見込んだ若手選手を獲得しやすくなるよう配慮された制度です。川崎フロンターレからトッテナムへ移籍した高井幸大選手のようなケースは、こうした若手向けのルールが適用された可能性があります。ただし、プレミアリーグのクラブが1シーズンに獲得できる21歳以下の外国籍選手は6人まで、という制限も設けられています。
女子サッカー(WSL)の労働許可証条件
近年、人気とレベルが急上昇しているイングランドの女子サッカーリーグ「FA女子スーパーリーグ(WSL)」にも、男子と同様に労働許可証の制度が存在します。長谷川唯選手(マンチェスター・シティ)や長野風花選手(リヴァプール)など、多くの日本人選手が活躍していますが、彼女たちもGBEの基準をクリアして移籍しています。
女子サッカーのGBEポイントシステムも、基本的には男子と似た構造になっています。評価の柱となるのは、やはり代表チームでの実績とクラブでの実績です。
- 代表での実績:女子FIFAランキングにおける自国の順位と、過去の代表戦での出場割合が評価されます。なでしこジャパン(日本女子代表)は世界的に見ても強豪国であるため、そこでコンスタントに出場している選手は高いポイントを得やすくなります。
- クラブでの実績:移籍元の所属リーグのレベルや、UEFA女子チャンピオンズリーグのような大陸選手権での出場実績が評価されます。
男子のプレミアリーグほどではありませんが、WSLも世界トップクラスの選手が集まるリーグへと成長しており、労働許可証の基準もそれに伴って整備されています。なでしこジャパンでの継続的な活躍が、WSLへの扉を開く上で非常に重要な要素となっているのです。
監督やスタッフの労働許可証
選手だけでなく、チームを率いる監督やコーチ、メディカルスタッフなどの専門職スタッフが外国籍である場合も、イギリスで働くためには就労ビザが必要になります。選手とは異なるカテゴリーのビザ(International Sportsperson visaなど)を申請することになりますが、その際にもFAなどの統括団体からの推薦(Endorsement)が求められます。
監督やコーチの場合、GBEのような厳格なポイント制とは少し異なりますが、その人物がイギリスのサッカー界に貢献できる高い能力や実績を持っているかが審査されます。具体的には、以下のような点が考慮されます。
- 指導者ライセンス:UEFAプロライセンスなど、国際的に認められた最高位の指導者資格を保有しているか。
- 指導実績:過去に国内外のトップリーグや代表チームで監督・コーチとしてどのような実績を残してきたか。
- クラブからの推薦:契約を希望するクラブが、なぜその指導者が必要なのかを具体的に説明する必要があります。
アーセナルのミケル・アルテタ監督(スペイン国籍)やマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督(スペイン国籍)のように、プレミアリーグでは多くの名将が活躍していますが、彼らもこうした厳格な審査を経て指導にあたっています。選手同様、スタッフにも「最高水準」が求められるのがプレミアリーグなのです。
まとめ:プレミアリーグの労働許可証の条件を理解し、移籍市場をもっと楽しもう

この記事では、プレミアリーグでプレーするために不可欠な労働許可証、すなわちGBE(統括団体による推薦)の仕組みと条件について詳しく解説してきました。
要点をまとめると以下のようになります。
- 外国籍選手がプレミアリーグでプレーするには、FAが発行するGBEが必要不可欠。
- GBE取得の基本は、代表やクラブでの実績を数値化したポイントシステムで、合計15ポイント以上が自動発給の目安。
- ポイントが足りない場合でも、例外パネル(ESC)による審査で認められる可能性がある。
- ブレグジットにより、EU国籍選手もGBEの対象となり、移籍のハードルが全体的に上がった。
- 日本人選手は、Jリーグから直接ではなく、欧州の他リーグで実績を積むことや、代表で活躍し続けることが移籍実現の重要なルートとなっている。
この複雑で厳しい労働許可証のルールは、プレミアリーグが「世界最高峰」であり続けるための仕組みの一つです。選手の移籍ニュースに触れたとき、このGBEの視点を持つことで、「なぜこの選手は移籍できたのか」「この若手選手はどの基準をクリアしたのだろう」といった、より深い見方でサッカーニュースを楽しめるようになるはずです。今後も、この高い壁に挑み、乗り越えていく日本人選手たちの挑戦に注目していきましょう。