サッカー観戦をしていると「あのボランチの選手、いい動きだな」「アンカーが効いているね」といった解説を耳にすることがありますよね。どちらも中盤の守備的なポジションを指す言葉ですが、その違いを正確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。
「アンカー」と「ボランチ」、この2つのポジションの違いを理解すると、サッカーの戦術的な側面がより深く見えてきて、観戦が何倍も面白くなります。この記事では、サッカーについて調べている方のために、アンカーとボランチの役割や動き方の違い、言葉の由来から具体的な有名選手まで、イラストや表を交えながら、やさしくわかりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたもきっと「なるほど!」と納得できるはずです。
アンカーとボランチの基本的な違い

サッカーの中盤、特に守備的な役割を担う選手を指して使われる「アンカー」と「ボランチ」という言葉。同じような意味で使われることもありますが、実はその由来や求められる役割には明確な違いがあります。 ここでは、まず2つのポジションの最も基本的な違いについて見ていきましょう。
言葉の由来と意味の違い
まず、2つの言葉の由来が異なります。
- ボランチ (Volante)
「ボランチ」はポルトガル語で「ハンドル」や「舵取り」を意味する言葉です。 チームの舵取り役として、攻守にわたって試合の流れをコントロールする重要な役割を担うことから、この名前で呼ばれるようになりました。 - アンカー (Anchor)
一方、「アンカー」は英語で船の「錨(いかり)」を意味します。 船が流されないように固定する錨のように、チームの守備が崩れないよう、ディフェンスラインの前にどっしりと構えて相手の攻撃を食い止める役割から来ています。
このように、「舵取り役」として攻守に関わるボランチと、「錨」として守備の安定を最優先するアンカーでは、言葉の由来からもその役割の違いがイメージできますね。
ピッチ上の基本的な位置取り
アンカーもボランチも、ポジションとしてはミッドフィルダー(MF)の中でも守備的な役割を担う「守備的ミッドフィルダー」に分類されます。 具体的な位置はディフェンダー(DF)の前、攻撃的なミッドフィルダー(MF)の後ろ、つまり中盤の底(そこ)と呼ばれるエリアです。
しかし、その中でも役割によって微妙に位置取りや動く範囲が変わってきます。
- ボランチ
ボランチは、守備だけでなく攻撃の組み立て(ビルドアップ)にも積極的に関わるため、より広い範囲を動くことが求められます。 状況に応じて、少し高い位置を取って攻撃に参加したり、サイドに流れて味方をサポートしたりと、攻守にわたってピッチを広くカバーします。 - アンカー
アンカーは、その名の通りディフェンスラインの前に錨を下ろすように、基本的にはセンターバック(CB)の前、バイタルエリアと呼ばれる危険なスペースを埋めることに専念します。 むやみにポジションを離れることは少なく、守備のバランスを保つことが最優先されます。
| ポジション | 主な活動エリア |
|---|---|
| ボランチ | 中盤の広い範囲(攻守に参加) |
| アンカー | ディフェンスラインの前(主に守備) |
求められる役割の根本的な違い
言葉の由来や位置取りの違いからもわかるように、アンカーとボランチではチームから求められる根本的な役割が異なります。
ボランチは、守備でボールを奪い、そこから攻撃の第一歩となるパスを出すなど、攻守の切り替えの起点となる役割を担います。 チーム全体のバランスを取りながら、試合の状況を読んで攻守両面でチームを支える、まさに「舵取り役」です。
一方、アンカーの第一の任務は守備です。 相手の攻撃の芽を摘み、ディフェンスラインへの負担を減らすことが最大のミッションです。 もちろん、ボールを奪った後には正確なパスで攻撃の起点となることも求められますが、その比重はボランチよりも守備に置かれています。
まとめると、「ボランチ」という大きな枠組みの中に、「アンカー」という、より守備に特化した役割が存在すると理解すると分かりやすいかもしれません。
「ボランチ」の具体的な役割とは?

ボランチは、ポルトガル語で「ハンドル」を意味する通り、チームの攻守の舵取りを担う非常に重要なポジションです。 ピッチの中央に位置し、試合の流れを読みながら攻守両面でチームを支えます。 ここでは、ボランチの具体的な役割をさらに詳しく見ていきましょう。
攻撃の起点となるビルドアップ
ボランチの攻撃における最も重要な役割の一つが、ビルドアップ、つまり後方のディフェンダーからボールを受け、攻撃を組み立てることです。
ディフェンダーの前に位置するボランチは、相手からのプレッシャーが比較的少ない状態でボールを受けられることが多く、そこから試合の状況を見ながら効果的なパスを前線に供給します。
具体的には、以下のようなプレーが求められます。
- 味方センターバックからのパスを受ける動き: 相手フォワードのプレッシャーを避け、安全にパスを受けられる位置に動きます。
- サイドへの展開: 相手の守備が中央に集中している場合、サイドバックやサイドハーフへパスを送り、攻撃の幅を広げます。
- 縦パス: 相手ディフェンスの隙を見つけて、フォワードへ一気にゴールに繋がるような鋭い縦パスを狙います。
ボランチのパス一本で、チームの攻撃は大きく変わります。 常に首を振って周りの状況を確認し、どこにパスを出せばチャンスが生まれるかを瞬時に判断する能力が不可欠です。
守備でのボール奪取とスペース管理
守備において、ボランチはディフェンスラインの前でフィルターとなり、相手の攻撃を食い止める役割を担います。 特に、ペナルティエリア手前の中央部分である「バイタルエリア」に相手選手を侵入させないことが重要です。 このエリアで自由にプレーさせてしまうと、決定的なシュートやパスに繋がる可能性が高まるためです。
ボランチの守備は、ただ相手にタックルするだけではありません。
- スペースを埋める: 味方が抜かれたり、ポジションがずれたりしてできた危険なスペースを素早くカバーします。
- パスコースを限定する: 相手のパスコースに立つことで、危険な場所へのパスを防ぎ、相手の攻撃を遅らせます。
- ボール奪取(インターセプト・タックル): 相手のパスを読んでカットしたり(インターセプト)、ドリブルしている相手からボールを奪ったりします(タックル)。
広い視野と危機察知能力を活かして、相手の攻撃の芽を未然に摘み取ることが、ボランチの守備における大きな役割です。
攻守のバランスを取るバランサー
ボランチは、ピッチの中央で攻守両面に関わるため、常にチーム全体のバランスを考える必要があります。 攻撃に参加している時でも、カウンター攻撃(守備から攻撃へ素早く切り替えること)を受けた場合に備えて守備の準備をしておく必要がありますし、守備をしている時でも、ボールを奪った後の攻撃の展開を考えておかなければなりません。
例えば、相方のセンターバックやサイドバックが攻撃参加で高い位置を取った場合、ボランチは少し下がり目の位置を取ってその裏のスペースをカバーします。 このように、味方の選手の動きを常に把握し、チーム全体の形が崩れないように調整するのが、バランサーとしてのボランチの重要な仕事です。 そのため、長時間走り続けられるスタミナや、的確なポジショニングを取るための戦術眼が求められます。
ダブルボランチの役割分担
現代サッカーでは、ボランチを2人置く「ダブルボランチ」のシステムが主流です。 2人いることで、中盤の守備をより強固にし、攻守のバランスを取りやすくなるというメリットがあります。
ダブルボランチでは、2人の選手がそれぞれ異なる役割を担うのが一般的です。
- 攻撃的な選手と守備的な選手の組み合わせ: 一人はパスやドリブルで攻撃を組み立てることを得意とし、もう一人はボール奪取やスペースのカバーなど守備的な役割に徹します。
- ボール奪取役とカバーリング役の組み合わせ: 一人が積極的に相手にプレッシャーをかけに行き、もう一人はその背後のスペースをカバーするという役割分担です。
「アンカー」の具体的な役割とは?
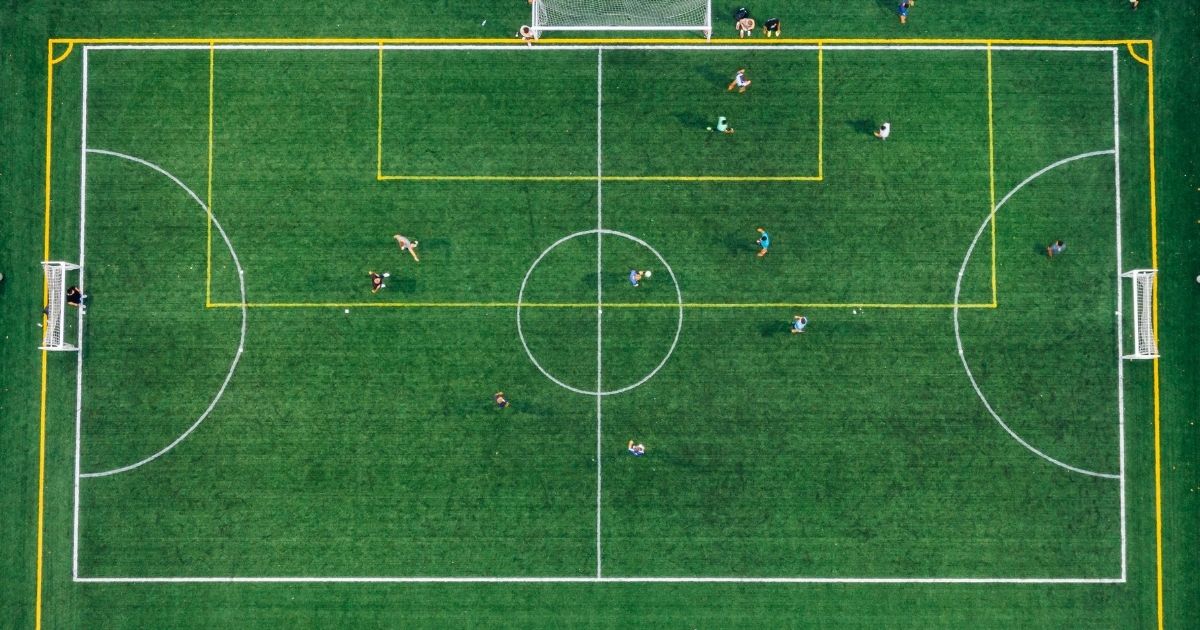
アンカーは、英語で「錨(いかり)」を意味する通り、ディフェンスラインの前にどっしりと構え、チームの守備を安定させることを最大の使命とするポジションです。 ボランチの中でも特に守備に重点を置いた役割であり、「守備のスペシャリスト」と言える存在です。
守備に特化したディフェンスの要
アンカーの最も重要な役割は、相手の攻撃を最終ラインに到達する前に食い止めることです。 センターバックの前という、ゴールに直結する危険なエリアを一人で守るため、非常に高い守備能力が求められます。
具体的には、以下のようなプレーでチームの守備に貢献します。
- 相手エースの監視: 相手チームの司令塔となる攻撃的ミッドフィルダーや、最前線から下がってくるフォワードの動きを常に監視し、自由にプレーさせません。
- 危険なスペースの察知とカバー: 相手が使おうとしている危険なスペースをいち早く察知し、そのスペースを埋めることで攻撃の芽を摘みます。
- ボール奪取: 激しいタックルや鋭い読みによるインターセプトでボールを奪い、相手の攻撃を終わらせます。
アンカーは、派手な攻撃参加は少ないものの、その存在によってチーム全体に安定感をもたらす、まさに縁の下の力持ちです。
ディフェンスライン前の防波堤
アンカーは、ディフェンスラインの前で「防波堤」のような役割を果たします。荒波(相手の攻撃)がディフェンスラインに直接打ちつけられるのを、その手前で防ぐのです。
アンカーがいることで、センターバックは相手フォワードとの1対1に集中でき、サイドバックはより安心して攻撃に参加できます。アンカーが中央の危険なエリアを一人でカバーしてくれるため、ディフェンダーは自分の持ち場を守ることに専念できるのです。
また、アンカーは守備のバランスを常に保つ役割も担います。 味方選手がボールを奪いに行って空けたスペースを埋めたり、チーム全体の守備組織が崩れないように指示を出したりと、守備の司令塔としての役割も期待されます。 そのため、高い危機察知能力と戦術理解度が不可欠です。
攻撃の第一歩を担う配球役
アンカーは守備専門の選手というわけではありません。ボールを奪った後には、攻撃の第一歩を担う重要な役割があります。 相手のプレッシャーが比較的少ない位置でボールを奪うことが多いため、そこから落ち着いて正確なパスを出すことで、効果的な攻撃に繋げることができます。
アンカーからのパスは、チームの攻撃の方向性を決定づけます。
- シンプルな繋ぎのパス: 近くの味方に確実にパスを繋ぎ、チーム全体でボールを保持して攻撃を組み立て直します。
- サイドチェンジ: 相手の守備が片方のサイドに寄っているのを見逃さず、逆サイドのオープンスペースへ大きく展開するパスを出します。
- 縦パス: 前線の選手の動き出しに合わせて、相手ディフェンスの背後を狙う鋭いパスを供給します。
1アンカーシステムの戦術的意味
ボランチを2人置く「ダブルボランチ」に対し、アンカーを1人だけ中盤の底に配置するシステムを「1アンカー(ワンアンカー)」と呼びます。 このシステムは、4-3-3フォーメーションなどで採用されることが多く、戦術的にいくつかの意味を持ちます。
- 攻撃的な選手の数を増やせる: 中盤の守備をアンカー1人に任せることで、その前のポジション(インサイドハーフなど)により攻撃的な選手を配置することができます。これにより、チーム全体の攻撃力を高める狙いがあります。
- ビルドアップの安定: アンカーがセンターバックの間に下りてパスを受けることで、後方でのボール回しがスムーズになり、相手のプレッシャーを回避しやすくなります。
- アンカーへの高い要求: このシステムを機能させるためには、アンカー役の選手に非常に高い能力が求められます。広い守備範囲、1対1の強さ、正確なパス能力、高い戦術理解度など、攻守両面で傑出したクオリティが必要です。
1アンカーシステムは、そのアンカーの選手の能力にチームの出来が大きく左右される、専門性の高い戦術と言えるでしょう。
有名選手で見るアンカーとボランチの違い

役割や動き方を言葉で説明されても、具体的なイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、世界や日本で活躍する有名選手を例に挙げて、アンカーとボランチのプレースタイルの違いを見ていきましょう。選手たちのプレーを思い浮かべることで、より深く理解できるはずです。
代表的なボランチの選手たち
ボランチは攻守にわたってチームを支えるバランサーです。ボール奪取能力に加えて、攻撃の起点となるパス能力も高い選手が揃っています。
- 遠藤 航(えんどう わたる)選手
日本代表のキャプテンも務める遠藤選手は、「デュエル(1対1)の強さ」が最大の武器です。 激しいボール奪取で相手の攻撃の芽を摘むだけでなく、ボールを奪った後には正確なパスで攻撃の起点にもなります。 豊富な運動量でピッチを広くカバーし、攻守両面でチームに貢献する、まさに現代サッカーにおける理想的なボランチの一人です。 - 守田 英正(もりた ひでまさ)選手
高い戦術理解度とパスセンスが光るボランチです。 危険なスペースを察知して埋めるポジショニングの良さと、相手の意表を突くような効果的なパスでチームの攻撃を操ります。ボールを奪う守備力と、攻撃を組み立てる展開力を高いレベルで兼ね備えています。 - ヨシュア・キミッヒ選手(ドイツ代表)
攻守のバランスに非常に優れた世界トップクラスのボランチです。 鋭い読みと力強い守備でボールを奪い取ると、視野の広さと高いパス精度を活かして、決定的なチャンスを演出します。 戦術眼も非常に高く、様々なポジションをこなせるユーティリティ性も魅力です。
代表的なアンカーの選手たち
アンカーは守備のスペシャリストであり、ディフェンスラインの前で防波堤となる役割を担います。危機察知能力とポジショニングの良さが際立つ選手たちです。
- セルヒオ・ブスケツ選手(元スペイン代表)
「アンカー」というポジションの概念を世界に知らしめた選手と言っても過言ではありません。 派手さはありませんが、抜群の予測能力とポジショニングで相手のパスコースを消し、ボールを奪い取ります。 ボールを奪った後も慌てることなく、シンプルなパスで味方に繋ぎ、チームに落ち着きをもたらす存在です。 - カゼミーロ選手(ブラジル代表)
強靭なフィジカルを活かした圧倒的なボール奪取能力を誇るアンカーです。 相手選手への激しいタックルでボールを刈り取り、中盤の門番として君臨します。守備的な役割に徹することが多いですが、時には強烈なミドルシュートでゴールを狙うなど、攻撃面でも貢献できる選手です。 - ロドリ選手(スペイン代表)
マンチェスター・シティ(イングランド)の守備の要です。 190cmを超える長身を活かした守備範囲の広さと、的確な戦況判断能力が持ち味です。 相手の攻撃を食い止めるだけでなく、正確な長短のパスで攻撃の起点となり、試合をコントロールします。
プレースタイルによるタイプの違い
同じボランチやアンカーというポジションでも、選手によって得意なプレーは様々です。大きく分けると、以下のようなタイプに分類できます。
| タイプ | 特徴 | 代表的な選手 |
|---|---|---|
| バランサータイプ | 攻守のバランスを取り、チームを安定させる。戦術理解度が高い。 | 遠藤 航、ヨシュア・キミッヒ |
| レジスタタイプ(司令塔型) | 中盤の低い位置から、長短のパスで攻撃を組み立てる。 | アンドレア・ピルロ(元イタリア代表) |
| クラッシャータイプ(潰し屋) | 激しいタックルやフィジカルの強さを活かし、相手の攻撃を潰す。 | カゼミーロ、エンゴロ・カンテ(元フランス代表) |
まとめ:アンカーとボランチの違いを知ってサッカー観戦をさらに楽しもう

今回は、サッカーの「アンカー」と「ボランチ」の違いについて解説しました。最後に、この記事の要点を振り返ってみましょう。
- 言葉の由来: ボランチは「舵取り」、アンカーは「錨」が語源。
- 主な役割: ボランチは攻守のバランスを取る「バランサー」、アンカーは守備に特化した「スペシャリスト」。
- 動き方の違い: ボランチは中盤を広く動き、アンカーはディフェンスラインの前にどっしり構える。
- 関係性: 「ボランチ」という広い枠組みの中に、より守備的な役割である「アンカー」が存在すると考えられる。
この2つのポジションの違いを理解することで、チームがどのような戦術で戦おうとしているのか、中盤の選手がどのような役割を担っているのかが見えてきます。
例えば、「今日は守備を固めるためにアンカータイプの選手を起用しているな」とか、「ダブルボランチの2人がうまく連携して攻守を支えているな」といった視点で試合を観ることができるようになります。
次にサッカーを観戦する機会があれば、ぜひ中盤の選手たちの動きに注目してみてください。彼らがチームの心臓として、いかに重要な役割を果たしているかがわかり、サッカーの奥深さや面白さをより一層感じられるはずです。



