サッカーの世界最高峰リーグ、プレミアリーグ。その華やかな舞台に憧れる選手は世界中にいますが、誰もが簡単にプレーできるわけではありません。特に、イギリスがEUから離脱した「ブレグジット」以降、選手の移籍や登録に関するルールは大きく変わりました。
かつて存在した「プレミアリーグのEU枠」という言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、現在その制度は実質的になくなっています。では、今のプレミアリーグではどのようなルールで外国人選手がプレーしているのでしょうか?
この記事では、ブレグジットによって様変わりしたプレミアリーグの選手登録ルール、特に「ホームググロウン制度」や新たに導入された「労働許可証」の仕組みについて、サッカーファンなら知っておきたい情報をやさしく、そして詳しく解説していきます。複雑な制度を理解すれば、移籍市場のニュースがもっと面白くなるはずです。
プレミアリーグの「EU枠」はもうない?ブレグジットがもたらした大変革

プレミアリーグの選手獲得ルールを語る上で、現在は切っても切れない関係にあるのが2021年1月の「ブレグジット(イギリスのEU離脱)」です。この歴史的な出来事によって、サッカー界のルールも大きな影響を受けました。
かつての「EU枠」とその役割
ブレグジット以前、プレミアリーグには明確な「外国人枠」というものは存在しませんでした。 しかし、選手の国籍によって扱いが異なっていたのが事実です。具体的には、EU(欧州連合)またはEFTA(欧州自由貿易連合)加盟国の国籍を持つ選手は、イギリス人選手とほぼ同じ扱いを受けていました。 彼らは労働許可証なしで自由にプレミアリーグのクラブと契約し、プレーすることができたのです。
一方で、それ以外の国(非EU/EFTA圏)の選手は、A代表での出場経験など、厳しい基準をクリアして「労働許可証」を取得する必要がありました。 つまり、実質的に「EU圏内選手は自由、それ以外の外国人選手は厳しい審査あり」という枠組みが存在しており、これが俗に「EU枠」と呼ばれるものの実態でした。このため、各クラブは実力のあるEU圏内選手を比較的容易に獲得でき、それがリーグ全体のレベル向上にも繋がっていたのです。
ブレグジットがもたらしたルールの激変
2021年1月、イギリスがEUから完全に離脱したことで、この状況は一変します。 これまでイギリス人選手と同じように扱われてきたEU加盟国の選手たちも、「外国人選手」として扱われることになったのです。
これにより、国籍に関わらず、すべての外国籍選手がプレミアリーグでプレーするためには、後述する「労働許可証(GBE)」を取得することが必須となりました。 つまり、これまでのような「EU枠」という優遇措置は完全に撤廃され、フランスやドイツ、スペインといったサッカー強国の選手であっても、日本人選手やブラジル人選手と同じ土俵で、厳格な基準に基づいた審査を受ける必要が出てきたのです。 この変更は、各クラブの補強戦略に非常に大きな影響を与えることになりました。
18歳未満の外国人選手の獲得が原則禁止に
ブレグジットによるもう一つの大きな変化は、若手選手の獲得ルールです。FIFAのルールでは、18歳未満の選手の国際移籍は原則禁止されていますが、EU・EEA(欧州経済領域)内では16歳から18歳の選手に限り移籍が認められる例外規定がありました。しかし、イギリスがEUを離脱したことで、この例外が適用されなくなりました。
その結果、プレミアリーグのクラブは、18歳未満の外国人選手(EU圏内も含む)を直接獲得することができなくなりました。 さらに、21歳以下の外国人選手の獲得も、1つの移籍市場で3人まで(年間最大6人)という制限が設けられています。 これまでヨーロッパ中から青田買いをしていきた才能ある若手選手を安価で獲得してきたプレミアリーグのクラブにとって、これは非常に大きな打撃となりました。将来有望な若手を早期に確保し、自クラブで育てるという戦略が取りにくくなったのです。
現在のプレミアリーグ選手登録の仕組み
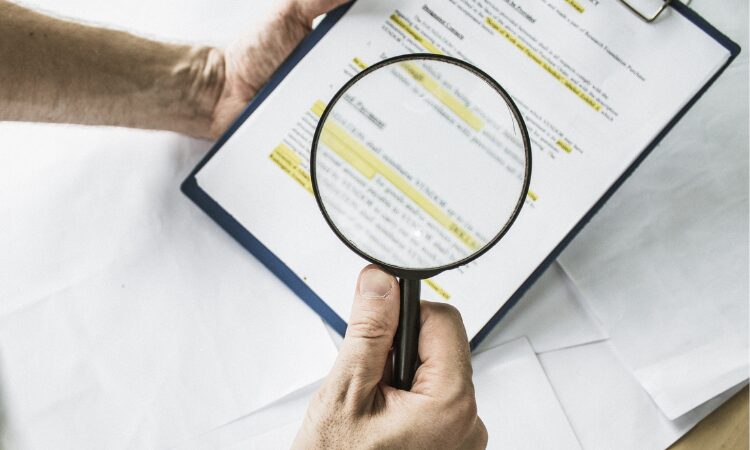
EU枠がなくなった今、プレミアリーグの選手登録はどのようなルールで成り立っているのでしょうか。現在の制度を理解する上で重要な2つの柱が「ホームグロウン制度」と「21歳以下の選手の扱い」です。
トップチームの登録は25名が上限
まず、プレミアリーグの各クラブがトップチームに登録できる選手(21歳以上)の数は、最大で25名と定められています。 この25名の枠をどのように構成するかが、各クラブの腕の見せ所となります。そして、この25名の中に必ず含めなければならないのが、「ホームグロウン選手」です。
具体的には、25名の登録枠のうち、ホームグロウン選手ではない選手(非ホームグロウン選手)は最大で17名までしか登録できません。 つまり、25名の枠をすべて使い切るためには、最低でも8名のホームグロウン選手を登録する必要があるのです。 もし、クラブがホームグロウン選手を8名確保できない場合、例えば6名しかいない場合は、登録できる選手数の上限が23名(17名 + 6名)に減ってしまう仕組みです。
トップチームの登録上限:25名
非ホームグロウン選手の登録上限:17名
* 25名枠を使い切るには、最低8名のホームグロウン選手が必要
「ホームグロウン選手」の詳しい定義
では、その「ホームグロウン選手」とは一体どのような選手を指すのでしょうか。ここで重要なのは、国籍は一切関係ないという点です。 「ホームグロウン」という言葉からイングランド出身選手を想像しがちですが、そうではありません。
ホームグロウン選手として認められるための条件は、「21歳の誕生日を迎えるまでに、国籍を問わず、イングランドまたはウェールズのクラブに継続していなくても合計で3シーズン(36ヶ月)以上在籍していた選手」と定義されています。
例えば、スペイン国籍のセスク・ファブレガス選手は、16歳でアーセナルに加入し長年プレーしたため、ホームグロウン選手として扱われます。逆に、イングランド代表のエリック・ダイアー選手のように、若い頃にポルトガルのクラブで育った選手は、イングランド国籍であってもホームグロウン選手には該当しません。 この制度は、国内で育成された選手の価値を高め、各クラブに若手育成を促す目的があります。
21歳以下の選手は「別枠」で無制限に登録可能
現在のプレミアリーグのルールで、もう一つ非常に重要なのが21歳以下の選手(U21選手)の扱いです。 シーズン開始時点で21歳に達していない選手は、前述した25名の登録枠とは別に、無制限でトップチームの試合に出場登録することができます。
このルールがあるため、多くのクラブは将来有望なU21選手を多数抱え、トップチームの戦力として活用しています。 例えば、20歳でワールドカップの最優秀若手選手に選ばれたエンソ・フェルナンデス選手(2001年1月17日生まれ)のようなスター選手も、22-23シーズンにチェルシーへ移籍した際はU21枠の対象でした。 このU21枠の存在が、クラブのスカッド編成に柔軟性をもたらし、若手選手の出場機会を創出する一因となっているのです。
新たな壁「労働許可証(GBE)」とは?

ブレグジット後、EU圏内の選手を含め、すべての外国籍選手に義務付けられたのが「労働許可証」の取得です。この許可証を得るための基準が「GBE(Governing Body Endorsement)」と呼ばれる、イングランドサッカー協会(FA)が定めたポイント制度です。
GBE(統括団体による推薦)のポイント制度
GBEとは、選手がプレミアリーグでプレーするに足る実力と実績を持っているかを客観的に評価するための仕組みです。 選手は様々な項目によってポイントを付与され、合計で15ポイント以上を獲得すると、原則としてGBEが自動的に発行されます。 もしポイントが10〜14ポイントだった場合は、例外パネルによる審査に回ることになります。
この制度は、単に選手の才能だけでなく、これまでのキャリアでどれだけ高いレベルでプレーし、実績を残してきたかを数値化するものです。 イギリス政府が「自国民の雇用を守りつつ、英国の社会に貢献できる優秀な人材かを見極める」という目的も背景にあります。
ポイントはどうやって決まる?評価項目を解説
GBEのポイントは、主に以下の6つのカテゴリーに基づいて計算されます。 クラブでの活躍と代表での実績の両方が重要視される仕組みです。
| カテゴリー | 評価内容の例 |
|---|---|
| 国際試合での実績 | ・過去2年間のA代表公式戦への出場割合 ・代表チームのFIFAランキング(ランキングが高いほど有利) |
| 所属クラブでの実績(国内リーグ) | ・過去1年間の国内リーグでの出場時間割合 ・所属リーグのレベル(FAが世界中のリーグを6段階にランク付け) |
| 所属クラブでの実績(大陸選手権) | ・UEFAチャンピオンズリーグやAFCチャンピオンズリーグなど、大陸別クラブ大会での出場時間割合 |
| 所属クラブの最終成績(国内リーグ) | ・所属クラブの国内リーグでの最終順位 |
| 所属クラブの最終成績(大陸選手権) | ・所属クラブが大陸選手権でどこまで勝ち進んだか |
| 所属リーグの質 | ・選手がプレーしているリーグ自体のレベル |
ポイントが足りなくても大丈夫?「ESCパネル」による救済措置
では、自動発行基準の15ポイントに届かなかった選手は、プレミアリーグでプレーする道を完全に断たれてしまうのでしょうか。実は、そうではありません。「例外パネル(Exceptions Panel)」、通称ESCパネルという仕組みが存在します。
これは、ポイントでは測れない特別な才能を持つ選手や、将来性が非常に高いと判断される若手選手などを個別に審査するための制度です。 クラブが「この選手は将来的にプレミアリーグで大きな貢献をする」と主張し、その根拠を提示することで、パネルが獲得の是非を判断します。
ただし、この審査は非常に厳格で、単に「才能がある」というだけでは許可は下りません。選手の経歴や市場価値、なぜGBEポイントが不足したのか、といった点を総合的に考慮して判断が下されます。あくまで例外的な措置であり、基本的には15ポイントを獲得することがプレミアリーグ移籍の前提となります。
ルール変更がクラブの補強戦略に与える影響

ブレグジットとそれに伴うGBE制度の導入は、プレミアリーグ各クラブの選手獲得戦略に大きな変化をもたらしました。これまでとは異なる視点での補強が求められるようになったのです。
若手有望株の獲得がよりシビアに
最も大きな影響を受けたのが、若手選手の獲得です。前述の通り、18歳未満の外国人選手が獲得できなくなったことに加え、18歳から21歳の選手であっても、トップチームでの出場経験や代表歴が少ないため、GBEの15ポイントを獲得するのは非常に困難です。
これにより、かつてのようにヨーロッパ中から10代の才能ある選手を安価で獲得し、自クラブのアカデミーでホームグロウン選手として育てる、という戦略が取りにくくなりました。クラブは、若手であっても既にある程度の実績を残し、GBEポイントを獲得できる見込みのある選手を狙うか、あるいは国内の若手選手の発掘・育成に、より一層力を入れる必要が出てきたのです。
即戦力となる各国代表クラスへの集中
GBEポイント制度は、各国代表チームでの出場歴や、レベルの高いリーグでの出場時間を高く評価します。 そのため、クラブの補強は必然的に、既に代表に定着している選手や、欧州主要リーグで主力として活躍している「即戦力」となる選手に集中する傾向が強まっています。
若くて将来性はあるものの、まだ実績の乏しい選手を獲得するリスクが高まったため、クラブはより確実性を求めるようになりました。これは、移籍金や選手の年俸が高騰する一因にもなっています。ワールドカップやEUROといった国際大会で活躍した選手が、その直後にプレミアリーグのクラブから注目を集めるのは、まさにこのGBEポイント制度が大きく影響していると言えるでしょう。
南米など非ヨーロッパ市場の価値向上
かつてはEU圏内の選手を労働許可証なしで自由に獲得できたため、プレミアリーグのスカウティングはヨーロッパ市場に偏りがちでした。 しかし、ブレグジットによってEUの優位性がなくなり、すべての外国人選手が同じGBEの基準で評価されるようになったことで、状況は変わりました。
ブラジルやアルゼンチンといった南米の強豪国は、代表チームのFIFAランキングが高く、多くの選手が若いうちからA代表でプレーする機会があります。そのため、彼らはGBEポイントを獲得しやすい傾向にあります。これにより、プレミアリーグのクラブにとって南米市場の魅力が相対的に高まり、これまで以上に積極的に南米の才能ある選手たちに注目するようになりました。ヨーロッパだけでなく、全世界にスカウト網を広げることが、これまで以上に重要になっているのです。
2023年に導入された新ルールとその狙い

厳格なGBE制度は、リーグの質を担保する一方で、才能ある若手の獲得を妨げているとの批判もありました。こうした状況を受け、イングランドサッカー協会(FA)は2023-24シーズンから、一部ルールを緩和する決定を下しました。
GBE基準を満たさない選手を限定的に獲得可能に
2023年6月、FAはGBEの自動発行基準(15ポイント)を満たさない選手であっても、各クラブが一定数獲得できる新たな枠を設けることを発表しました。 これにより、ポイントはわずかに足りないものの、クラブが将来性を高く評価する選手と契約できる道が開かれました。
この新しい枠の数は、各クラブが過去のシーズンでイングランド人選手にどれだけの出場時間を与えてきたかによって変動します。 基本的には最大で4人の選手を獲得できますが、イングランド人選手の出場機会が少ないクラブは、枠の数が2人などに制限される仕組みです。 このルール改定は、プレミアリーグの国際的な競争力を維持しつつ、イングランド人選手の育成も促すという、バランスを取った施策と言えます。
Jリーグの評価向上など、日本人選手への影響は?
このルール改定と同時に、GBEポイントの計算基準にも見直しが入りました。その中で、日本のサッカーファンにとって嬉しいニュースとなったのが、J1リーグのリーグレベル評価が引き上げられたことです。
これまでJリーグは、FAが定める6段階のリーグレベルの中で最も低い「バンド6」に分類されていました。 これが「バンド5」に引き上げられたことで、Jリーグで活躍する選手が、国内リーグでの出場実績やクラブの成績によって、以前よりも多くのGBEポイントを獲得できるようになったのです。 これは、将来的に日本人選手がプレミアリーグに挑戦する上で、間違いなく追い風となるでしょう。三笘薫選手や遠藤航選手、冨安健洋選手に続く、新たな日本人プレミアリーガーの誕生が、これまで以上に期待されます。
若手育成とリーグの魅力維持のバランス
一連のルール変更や緩和は、FAやプレミアリーグが常に「国内選手の育成」と「リーグの国際的な魅力・競争力の維持」という2つのテーマのバランスを模索していることを示しています。
厳しすぎるルールは世界中からスター選手が集まるプレミアリーグの魅力を損ないかねませんが、緩すぎれば国内の若手の出場機会が失われ、イングランド代表の弱体化に繋がる恐れがあります。 ブレグジットという大きな変化を経て、プレミアリーグは今も、世界最高峰のリーグであり続けるために、最適なルールとは何かを問い続けているのです。今後も、状況に応じてルールが見直されていく可能性は十分に考えられます。
まとめ:プレミアリーグのEU枠なき新時代の選手獲得戦略

この記事では、ブレグジット後のプレミアリーグにおける外国人選手の登録ルールについて解説しました。最後に、重要なポイントを振り返ってみましょう。
- EU枠の廃止:ブレグジットにより、かつて存在したEU圏内選手への優遇措置はなくなり、全ての外国人選手が同じルール下に置かれることになりました。
- ホームグロウン制度:国籍を問わず、21歳までに3年以上イングランドかウェールズで育成された選手を8名以上登録する必要があります。
- 労働許可証(GBE):全ての外国人選手は、代表やクラブでの実績をポイント化したGBEを取得しなければなりません。
- 若手獲得の難化と戦略の変化:18歳未満の外国人選手は獲得禁止となり、若手であっても実績が求められるようになったため、クラブの補強は即戦力中心へとシフトしています。
- 新ルールの導入:2023年からはGBE基準を満たさない選手を限定的に獲得できる枠が設けられ、Jリーグの評価も上がるなど、一部ルールが緩和されました。
プレミアリーグの「EU枠」という概念は過去のものとなり、現在はより複雑で戦略的な選手登録ルールが採用されています。これらのルールを理解することで、各クラブの移籍市場での動きや、チーム編成の意図がより深く見えてくるはずです。今後のプレミアリーグ観戦が、さらに楽しくなる一助となれば幸いです。



