スペインのプロサッカーリーグ、ラ・リーガで選手たちが華麗なプレーを繰り広げる裏側には、チーム編成を左右する重要なルールが存在します。それが「外国人枠」です。このルールは、どの国の選手を何人までチームに登録できるかを定めたもので、特にEU(欧州連合)圏外の国籍を持つ選手にとっては、ラ・リーガ移籍の大きな壁となることがあります。
なぜこのような枠が存在するのでしょうか?そして、EU圏内と圏外では何が違うのでしょうか?この記事では、ラ・リーガの外国人枠の基本的な仕組みから、日本人選手にも深く関わる特例や他リーグとの比較まで、サッカー観戦がもっと面白くなる知識をわかりやすく解説していきます。
ラ・リーガの外国人枠に関する基本ルール

ラ・リーガのチーム作りを理解する上で欠かせないのが「外国人枠」の存在です。このルールは、クラブが登録できる選手の国籍を制限するもので、特にEU圏外の選手獲得に大きな影響を与えます。ここでは、その基本的なルールと目的について見ていきましょう。
EU圏外(非EU)国籍選手は最大3人まで
ラ・リーガにおける外国人枠の最も重要なポイントは、各チームが登録できるEU圏外の国籍を持つ選手の数が最大3人までと定められていることです。 これは、試合に出場できる選手だけでなく、チームに登録する選手全体の数に対する制限です。
この厳しい制限があるからこそ、ラ・リーガのクラブは世界中から本当に価値のある選手を厳選する必要があり、それがリーグ全体のレベルを高く保つ一因にもなっています。
EU圏内国籍選手は外国人枠に含まれない
一方で、EU加盟国の国籍を持つ選手は、ラ・リーガでは外国人として扱われません。 これは、1995年の「ボスマン判決」というヨーロッパのサッカー界を大きく変えた判例に基づいています。 この判決により、EU圏内では選手の移動の自由が保障され、EU国籍を持つ選手はどの加盟国のリーグでも自国の選手と同じようにプレーできるようになりました。
そのため、フランス、ドイツ、イタリアといったサッカー強国の選手はもちろん、他のEU加盟国の選手であれば、何人でもチームに登録することが可能です。 このルールにより、EU圏内の選手は移籍の選択肢が広がり、多くのクラブで多様な国籍の選手が活躍する現在のヨーロッパサッカーの姿が形作られました。
なぜ外国人枠が存在するのか?その目的
外国人枠が存在する主な目的は、自国の選手を保護し、育成を促進することにあります。 もし外国人枠がなければ、資金力のあるクラブが世界中からスター選手を買い集め、自国の若手選手が出場機会を失ってしまう可能性があります。
外国人枠を設けることで、各クラブは国内の才能ある若手選手にも目を向け、育成に力を入れるようになります。 これが、スペイン代表が長年にわたって国際舞台で強さを維持している要因の一つとも言えるでしょう。また、リーグ内の戦力均衡を保ち、特定のクラブだけが突出して強くならないようにする役割も担っています。 このように、外国人枠は単なる制限ではなく、リーグ全体の健全な発展と競争力を維持するために不可欠なルールなのです。
外国人枠には特例がある!「ACP加盟国」とは?
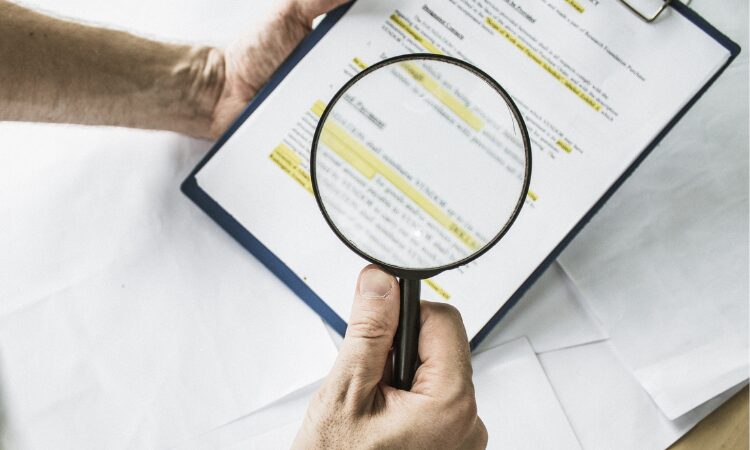
ラ・リーガの外国人枠は「EU圏外選手は3人まで」というのが基本ですが、実はいくつかの特例が存在します。その中でも特に重要なのが「ACP加盟国」の選手に関する扱いです。この特例を理解することで、なぜ特定のアフリカ出身選手などが外国人枠にカウントされないのかが分かります。
ACP加盟国とは?アフリカ・カリブ海・太平洋諸国の選手たち
ACP加盟国とは、アフリカ(African)、カリブ海(Caribbean)、太平洋(Pacific)地域の国々の総称です。具体的には、アフリカの多くの国々や、ジャマイカのようなカリブ海の国、フィジーのような太平洋の島国などが含まれています。
これらの国々の選手は、地理的にはEU圏外ですが、後述する特別な協定により、ラ・リーガではEU圏内選手と同じように扱われることがあります。 そのため、例えばセネガルやコートジボワールといった国籍の選手は、EU圏外枠の3人にはカウントされず、クラブはより多くの外国籍選手を獲得することが可能になります。
コトヌー協定がもたらした影響
ACP加盟国の選手が特例扱いされる背景には、「コトヌー協定」という国際協定があります。 この協定は、EUとACP諸国との間で結ばれたもので、経済的な協力や発展を目的としています。
サッカーの世界では、この協定が選手の労働に関する部分にも影響を及ぼしました。「EU圏内では労働者の移動は自由」という原則が、この協定によってACP諸国の選手にも適用されると解釈されたのです。 その結果、ACP諸国の国籍を持つ選手は、EU圏内の選手と同様に扱われ、外国人枠の制限を受けずにプレーできるようになりました。この協定は、多くのアフリカ出身選手がヨーロッパの舞台で活躍する道を開いた、非常に重要なものなのです。
ACP加盟国の選手がEU圏内選手と同じ扱いになる理由
コトヌー協定に基づき、EUの裁判所で「ACP諸国の国民も、EU域内での労働において差別されてはならない」という判決(コルパック判決)が出ました。 これにより、プロサッカー選手も労働者である以上、国籍を理由にEU圏外選手として出場を制限することは差別にあたるとされたのです。
スペイン国籍取得による外国人枠からの解放

外国人枠を回避するためのもう一つの重要な方法が、選手のスペイン国籍取得です。特に、ラ・リーガで長年活躍する南米出身のスター選手たちが、この方法で外国人枠から外れるケースが多く見られます。これにより、クラブは新たなEU圏外選手を獲得するための枠を確保することができます。
スペイン国籍を取得するための条件
スペインの国籍法では、外国人が国籍を取得するための条件が定められています。サッカー選手の場合、最も一般的なのは居住年数によるものです。原則として、スペインに継続して10年間居住することで、国籍取得の申請資格が生まれます。
しかし、これには例外があります。ブラジル、アルゼンチン、ペルーといったイベロアメリカ諸国や、旧植民地であったフィリピンなどの国籍を持つ人は、居住年数が2年に短縮されます。 このため、ブラジルやアルゼンチン出身の選手は、他の国出身の選手に比べて比較的早くスペイン国籍を取得できるのです。 国籍取得には、スペイン語の試験やスペインの文化・社会に関する試験に合格する必要もありますが、多くの選手がこの条件をクリアして国籍を取得しています。
南米出身選手が比較的早く国籍を取得できる「二重国籍」の仕組み
スペインは多くのイベロアメリカ諸国との間で二重国籍を認める協定を結んでいます。これにより、例えばブラジル国籍の選手がスペイン国籍を取得した場合、元のブラジル国籍を放棄する必要がありません。
この「二重国籍」が認められていることが、南米出身選手にとって大きなメリットとなっています。彼らは母国の代表としてプレーする権利を失うことなく、クラブではスペイン国籍選手(EU圏内選手)として登録されることができるのです。これにより、選手個人はキャリアの選択肢を広げられ、クラブは貴重な外国人枠を新たに活用できるという、双方にとって有利な状況が生まれます。
レアル・マドリードのスター選手たちの事例
この国籍取得の恩恵を最も象徴しているのが、世界的ビッグクラブのレアル・マドリードです。近年、チームの主力を担ってきたブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオール選手、ロドリゴ・ゴエス選手、エデル・ミリトン選手は、全員が加入後にスペイン国籍を取得しました。
彼らが加入した当初は、3人で3つのEU圏外枠をすべて占めていました。 しかし、2年間の居住条件を満たした後、順次スペイン国籍を取得したことで、レアル・マドリードは外国人枠に空きを作ることができました。 これにより、クラブは将来的に新たなEU圏外の才能ある若手選手を獲得するための柔軟性を手に入れたのです。 このように、選手の国籍取得は、クラブの長期的な補強戦略において非常に重要な要素となっています。
日本人選手とラ・リーガ外国人枠の関係

厳しい外国人枠は、ラ・リーガでの活躍を目指す日本人選手にとって、常に大きな壁として立ちはだかってきました。ここでは、日本を代表する選手たちがどのようにこの問題と向き合ってきたのか、そしてなぜ日本人選手にとってラ・リーガ移籍が難しいのかを掘り下げていきます。
久保建英選手が直面した外国人枠の壁
現在、レアル・ソシエダで輝きを放つ久保建英選手も、外国人枠に苦しんだ一人です。 2019年に名門レアル・マドリードに加入した際、クラブのEU圏外枠はすでにブラジル人選手たちで埋まっていました。
また、久保選手はインタビューで、日本では二重国籍が認められていないため、スペイン国籍を取得して枠を回避することが難しいという点にも言及しており、日本人選手特有の難しさも浮き彫りになっています。
柴崎岳選手など他の日本人選手のケース
久保選手以前にも、多くの日本人選手がスペインの地で挑戦してきました。例えば、柴崎岳選手はヘタフェ時代に名門FCバルセロナから鮮やかなゴールを決めるなど、印象的な活躍を見せました。しかし、彼もまた外国人枠の壁の中で厳しい競争を強いられた選手の一人です。
過去には、中村俊輔選手、大久保嘉人選手、乾貴士選手といった日本を代表する選手たちもラ・リーガでプレーしましたが、コンスタントにトップレベルで活躍し続けることの難しさに直面しました。 これは、単に実力だけの問題ではなく、貴重な3つの外国人枠の1つを勝ち取るためには、他の南米やアフリカのスター選手たちと競い合い、圧倒的な個の力を見せつける必要があるからです。日本人選手がこの厳しい環境でポジションを確保することは、決して簡単なことではないのです。
なぜ日本人選手にとってラ・リーガ移籍は難しいのか?
日本人選手にとってラ・リーガへの移籍が難しい理由は、主に3つ考えられます。
- 厳しい外国人枠(EU圏外枠)
これまで述べてきた通り、わずか3枠しかないEU圏外枠が最大の障壁です。 クラブは、得点力のあるフォワードや、将来的に高額で売却が見込める若い才能にこの枠を使いたいと考える傾向があり、日本人選手が割って入るのは容易ではありません。 - 南米選手との競合
言語や文化の面でスペインに馴染みやすく、さらに短期間でスペイン国籍を取得できる南米の選手は、クラブにとって非常に魅力的な存在です。 同じEU圏外枠を争う上で、日本人選手は南米のライバルたちよりも不利な条件にあると言えます。 - 過去の実績
これまでブンデスリーガ(ドイツ)では香川真司選手のように多くの日本人選手が成功を収め、日本人ブランドを確立してきました。 一方で、ラ・リーガではまだ絶対的な成功例が少なく、クラブのスカウトが日本人選手の獲得に慎重になる傾向があります。
これらの要因が複雑に絡み合い、日本人選手にとってラ・リーガは欧州の主要リーグの中でも特に挑戦のハードルが高いリーグとなっているのです。
他の欧州リーグとの外国人枠比較

ラ・リーガの外国人枠は非常に厳しいことで知られていますが、他のヨーロッパの主要リーグではどのようなルールが採用されているのでしょうか。各リーグの特色を知ることで、ラ・リーガの厳しさがより明確になります。
プレミアリーグ(イングランド)の労働許可証制度
イングランドのプレミアリーグには、ラ・リーгаのような明確な外国人枠の人数制限はありません。 しかし、その代わりに「労働許可証」という非常に厳しい制度が存在します。
EU圏外の選手がプレミアリーグでプレーするためには、英国政府から労働許可証を取得する必要があります。この許可証は、選手の代表キャップ数(国代表での試合出場数)や、代表チームのFIFAランキングなどをポイント化し、基準を満たした選手にのみ発行されます。 日本のようにFIFAランキングが比較的低い国の選手は、代表チームで主力としてコンスタントに出場し続けていないと、この基準をクリアするのが非常に困難です。 そのため、人数制限はないものの、実質的にはトップレベルの代表選手でなければ移籍が難しいという、ラ・リーガとは異なる種類の厳しさがあります。
セリエA(イタリア)の複雑な外国人枠
イタリアのセリエAの外国人枠は、非常に複雑なことで知られています。基本的な考え方として、すでにEU圏外選手を保有しているかどうかで、そのシーズンに新たに獲得できるEU圏外選手の数が変わってきます。
- EU圏外選手が0人の場合:最大3人まで獲得可能
- EU圏外選手が1人の場合:最大2人まで獲得可能
- EU圏外選手が2人以上の場合:最大2人まで獲得可能(ただし、1人は代表キャップなどの条件を満たす必要があり、もう1人は保有するEU圏外選手を放出することが条件)
このように、選手の入れ替えも考慮しなければならない複雑なルールになっています。 また、セリエAでは国内で育成された選手(ホームグロウン)を一定数登録する義務もあり、チーム編成の自由度は他のリーグに比べて低いと言えるかもしれません。
ブンデスリーガ(ドイツ)の比較的緩やかなルール
ドイツのブンデスリーガは、ヨーロッパの主要リーグの中で外国人枠のルールが比較的緩やかです。2006年にEU圏外選手の枠を撤廃し、代わりに「ドイツ人枠」を設けました。
| リーグ | 外国人枠(EU圏外枠)の主なルール |
|---|---|
| ラ・リーガ(スペイン) | EU圏外選手の登録は最大3人まで。 |
| プレミアリーグ(イングランド) | 人数制限はないが、厳しい労働許可証の取得が必要。 |
| セリエA(イタリア) | EU圏外選手の保有数によって、新規獲得枠が変動する複雑なルール。 |
| ブンデスリーガ(ドイツ) | EU圏外枠は撤廃。ただし、12人以上のドイツ国籍選手の登録義務あり。 |
まとめ:ラ・リーガの外国人枠を理解して、もっとサッカー観戦を楽しもう!

この記事では、ラ・リーガの外国人枠について、その基本ルールから特例、そして日本人選手への影響までを詳しく解説してきました。
要点をまとめると以下のようになります。
- ラ・リーガでは、EU圏外の選手は各チーム3人までしか登録できない。
- EU加盟国の国籍を持つ選手や、ACP加盟国の選手は外国人枠に含まれない。
- ブラジルなど特定の国の選手は、スペインに2年間居住することで国籍取得の道が開け、枠から外れることができる。
- この厳しい外国人枠が、久保建英選手をはじめとする日本人選手にとって大きな壁となってきた。
- ブンデスリーガなど他のリーグに比べて、ラ・リーガの外国人枠は特に厳しいルールである。
一見すると複雑なルールですが、この外国人枠の存在が、各クラブの補強戦略や、若手選手の育成方針に大きな影響を与えています。どの選手が外国人枠で、クラブはその貴重な枠を誰に使うのか。こうした視点を持つことで、移籍市場のニュースや試合のメンバー構成がより深く理解できるようになり、ラ・リーガの観戦がさらに面白くなるはずです。



