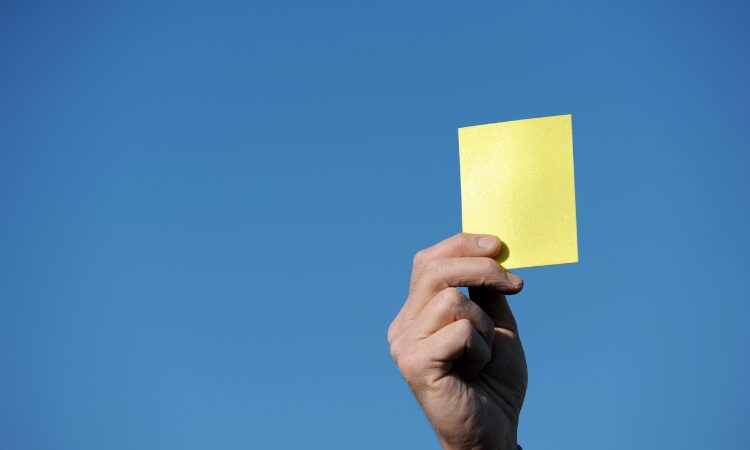サッカーの試合を観戦していると、審判が選手に黄色いカードを提示する場面をよく見かけますよね。あれが「イエローカード」です。このカードには「警告」という意味があり、選手が反則をしたり、非紳士的な行為をしたりしたときに出されます。 では、このイエローカードが一体何枚出されると、選手はプレーを続けられなくなるのでしょうか?
この記事では、「イエローカードを何枚もらうとどうなるのか?」という基本的な疑問から、Jリーグやワールドカップといった主要な大会ごとの累積枚数による出場停止ルール、さらにはイエローカードが提示される具体的な反則行為まで、サッカー初心者の方にも分かりやすく解説していきます。ルールを深く知ることで、サッカー観戦がもっと面白くなること間違いなしです。
イエローカードは何枚で退場?基本的なルールを知ろう

まずは、イエローカードに関する最も基本的なルールから見ていきましょう。1試合の中での枚数と、大会を通した累積枚数では、その後のペナルティが大きく異なります。
1試合に2枚もらうと退場処分に
1試合の中で、同じ選手がイエローカードを2枚提示されると、レッドカードが提示されて「退場」となります。
退場処分を受けた選手は、その試合に再び出場することはできません。 さらに、チームはその選手を補充することができないため、残りの試合時間を1人少ない人数で戦わなければならなくなります。 この数的不利はチームにとって非常に大きな痛手となります。
また、イエローカードを2枚もらって退場した場合、原則として次の1試合が出場停止になるというペナルティも科せられます。
イエローカードとレッドカードの違い
イエローカードとレッドカードは、どちらも審判が選手に提示するカードですが、その意味合いは大きく異なります。
- イエローカード: 「警告」を意味します。 反則行為や非紳士的行為に対して出され、次に同じような行為をすれば退場になる可能性があることを示唆します。
- レッドカード: 「退場」を意味します。 非常に悪質なファールや暴力行為など、重大な違反があった場合に一発で提示されることがあります。 また、前述の通り、1試合にイエローカードを2枚受けた場合にも提示されます。
簡単に言えば、イエローカードは「次はないですよ」という最後の警告、レッドカードは「一発アウト」の退場処分と覚えておくと分かりやすいでしょう。
| カードの種類 | 意味 | 提示されるケース | 提示後のペナルティ |
|---|---|---|---|
| イエローカード | 警告 | 反スポーツ的行為、異議、遅延行為など | 1枚目ではなし。ただし累積により出場停止の可能性あり。 |
| レッドカード | 退場 | 著しく不正なプレー、乱暴な行為、1試合にイエローカード2枚など | 即時退場。チームは人数が減る。次の試合も出場停止になる。 |
大会をまたいだ累積とリセットのタイミング
イエローカードのルールで少し複雑なのが、「累積警告」による出場停止です。 これは、リーグ戦やカップ戦などの同一大会において、受けたイエローカードの枚数が規定数に達すると、次の試合に出場できなくなるというルールです。
この累積枚数やリセットされるタイミングは、大会のレギュレーションによって異なります。例えば、Jリーグではシーズンを通して累積されますが、ワールドカップや天皇杯では特定のステージでリセットされることがあります。
重要なのは、異なる大会間ではイエローカードの累積は引き継がれないということです。例えば、Jリーグで受けたイエローカードが、天皇杯の試合に影響することはありません。
イエローカードが提示される具体的な反則行為

では、具体的にどのような行為をするとイエローカードが出されるのでしょうか。サッカー競技規則では、警告の対象となる行為が定められています。 ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
「反スポーツ的行為」とは?
「反スポーツ的行為」は、イエローカードの対象として最も頻繁に見られるものの一つです。 これには様々な行為が含まれます。
- 無謀なプレー: 相手選手への危険を顧みないタックルなど。
- 相手の大きなチャンスを妨害する: 「SPA(Stopping a Promising Attack)」と呼ばれ、決定機ではないものの、有望な攻撃を反則によって阻止する行為です。
- シミュレーション: ファールを受けていないのに、大げさに倒れて審判を欺こうとする行為。
- 過度なゴールパフォーマンス: ユニフォームを脱いだり、長時間にわたって喜びを表現したりする行為も警告の対象となります。
これらの行為は、サッカーの精神に反し、試合の公平性を損なう可能性があるため、警告の対象とされています。
「異議」や「遅延行為」も対象に
選手が審判の判定に対して、言葉やジェスチャーで過度に抗議する「異議」もイエローカードの対象です。 審判へのリスペクトを欠く行為と見なされます。
また、「遅延行為」も警告の対象となります。 これは、自分たちのチームがリードしている場面などで、意図的に時間を稼ぐ行為を指します。
- フリーキックやスローインをなかなか再開しない。
- ボールを遠くに蹴ったり、手で持って離さなかったりする。
- 選手交代の際に、ゆっくりとピッチから出る。
これらの行為は、試合のスムーズな進行を妨げるため、厳しく罰せられます。
ファウルを繰り返す行為
一つ一つの反則は軽くても、同じ選手が何度もファウルを繰り返す場合、審判は「繰り返し反則を犯す」としてイエローカードを提示することがあります。 どのくらいの回数で警告となるか明確な基準はなく、試合の流れやファウルの内容を考慮して主審が判断します。
審判は、反則が繰り返される選手に対して、口頭で注意した後にカードを提示することが一般的です。これは、選手にプレーの改善を促すための警告でもあります。
大会ごとの累積警告ルール【Jリーグ・ワールドカップなど】

イエローカードの累積による出場停止ルールは、大会によって枚数やリセットのタイミングが異なります。ここでは、主要な大会のルールを見ていきましょう。
Jリーグの出場停止ルール
日本のプロサッカーリーグであるJリーグ(J1、J2、J3共通)では、イエローカードの累積が4枚に達すると、次の1試合が出場停止となります。
出場停止処分を受けると、それまでの累積枚数はリセットされ、再び0からのカウントとなります。 例えば、4枚目のイエローカードで出場停止になった選手は、その次の試合からまた警告を受けなければ、出場停止にはなりません。ただし、シーズン中に2度目の累積4枚(通算8枚目)に達した場合は、2試合の出場停止というように、回数を重ねるごとにペナルティが重くなる規定もあります。
なお、YBCルヴァンカップでは累積2枚で次の1試合が出場停止となりますが、グループステージとプライムステージ(決勝トーナメント)で累積は引き継がれません。
天皇杯の出場停止ルール
天皇杯では、イエローカードの累積が2枚に達すると、次の1試合が出場停止となります。
天皇杯の大きな特徴は、準々決勝が終了した時点で、それまでのイエローカードの累積がリセットされる点です。
これにより、準決勝や決勝といった重要な試合で、主力選手が累積警告によって出場できないという事態を極力避けられるよう配慮されています。
ワールドカップ(W杯)の出場停止ルール
4年に一度開催されるサッカーの祭典、FIFAワールドカップでは、異なる2試合でイエローカードを受けると(累積2枚)、次の1試合が出場停止となります。
ワールドカップでも天皇杯と同様に、累積がリセットされるタイミングが設けられています。 具体的には、準々決勝が終了した時点で、それまでの警告がリセットされます。 これにより、選手たちは準決勝や決勝で警告を過度に恐れることなく、全力でプレーできるようになっています。
海外主要リーグの出場停止ルール
海外の主要なサッカーリーグでも、それぞれ独自の累積警告ルールが定められています。
- プレミアリーグ(イングランド): シーズンをいくつかの期間に区切っており、例えば19節までに5枚で1試合、32節までに10枚で2試合の出場停止といった段階的なルールが採用されています。
- ラ・リーガ(スペイン): 累積5枚で次の1試合が出場停止となります。
- セリエA(イタリア): 初めは累積5枚で出場停止ですが、一度出場停止になると、次は4枚、その次は3枚と、出場停止になるまでのハードルが下がっていくという特徴的なルールがあります。
イエローカードにまつわる豆知識と歴史

試合の流れを大きく左右するイエローカードですが、その誕生には興味深い背景があります。ここでは、イエローカードに関する豆知識をいくつかご紹介します。
イエローカードはいつから導入された?
イエローカードとレッドカードが初めて国際大会で導入されたのは、1970年のメキシコワールドカップからです。
このカード制度を考案したのは、イギリス人の審判、ケン・アストン氏です。 1966年のワールドカップで、言葉の通じない選手に退場を命じる際に混乱が生じた経験から、誰にでも分かりやすい視覚的なサインの必要性を感じました。 彼は帰宅途中の信号機を見て、黄色(注意)と赤(止まれ)のアイデアを思いついたと言われています。 この発明により、言語の壁を越えて、選手や観客が審判の判定を瞬時に理解できるようになったのです。
イエローカードとレッドカードがないスポーツは?
サッカー以外にも、ラグビー、ハンドボール、バレーボールなど多くのスポーツでイエローカードやレッドカードは採用されています。 それぞれのスポーツでカードの意味合いは少しずつ異なりますが、「警告」や「退場」といった基本的な概念は共通しています。
一方で、野球やバスケットボールのように、審判がカードを使わずに選手に退場を命じるスポーツもあります。これらのスポーツでは、審判のジェスチャーや宣告によって判定が示されます。
フェアプレーポイントとの関係
ワールドカップなどの大会では、「フェアプレーポイント」という制度が順位決定の際に用いられることがあります。これは、試合中のイエローカードやレッドカードの枚数をポイント化し、その少なさを競うものです。
- イエローカード1枚:マイナス1ポイント
- イエローカード2枚による退場:マイナス3ポイント
- 一発レッドカード:マイナス4ポイント
- イエローカード後のレッドカード:マイナス5ポイント
グループステージで勝ち点、得失点差、総得点などがすべて並んだ場合、このフェアプレーポイントが少ないチーム(=反則が少ないチーム)が上位となります。実際に2018年のワールドカップでは、日本代表がこのルールによってセネガルを上回り、決勝トーナメントに進出したことは記憶に新しいです。
まとめ:イエローカードを何枚もらうとどうなるか正しく理解しよう

この記事では、「イエローカード何枚」というキーワードを軸に、サッカーの警告に関するルールを詳しく解説してきました。
- 1試合でイエローカードを2枚もらうと退場になる。
- リーグや大会ごとに累積枚数が決められており、それに達すると出場停止になる。
- Jリーグでは4枚、ワールドカップでは2枚の累積で出場停止となるのが基本。
- イエローカードは、危険なプレーだけでなく、審判への異議や遅延行為など「反スポーツ的行為」に対しても提示される。
イエローカードのルールを理解することで、なぜ試合が止まったのか、なぜ選手が交代するのかといった、試合中の出来事の背景がより深く分かるようになります。次にサッカーを観戦する際は、ぜひ審判が提示するカードの色とその意味にも注目してみてください。きっと、新たな発見があるはずです。