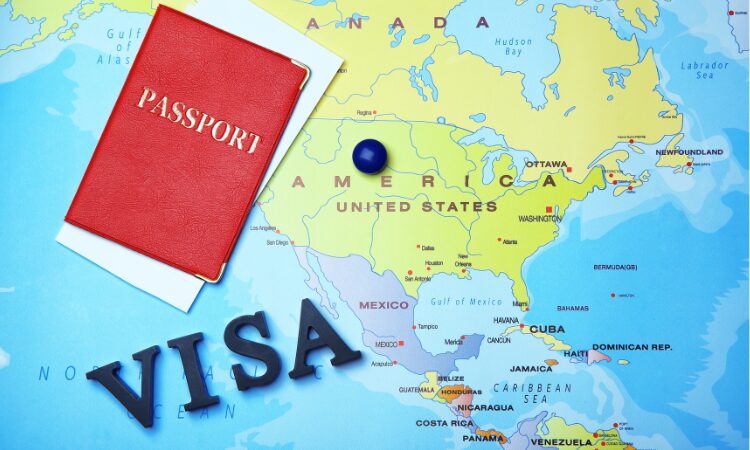世界最高峰のサッカーリーグと称されるイングランドのプレミアリーグ。華麗なプレーでファンを魅了するスター選手たちが数多く所属していますが、実は彼らがプレミアリーグのピッチに立つまでには、非常に厳しい「就”労ビザ」という壁を乗り越えなければなりません。
特に2021年のイギリスのEU離脱(ブレグジット)以降、そのルールはさらに複雑化しました。かつては比較的容易に移籍できたEU国籍の選手も、今では日本人選手と同じように厳しい審査の対象となっています。
なぜ三笘薫選手はブライトン加入後すぐにベルギーへレンタル移籍したのか?なぜ有望な若手選手が直接プレミアリーグのクラブと契約できないことがあるのか?その答えはすべて、この就労ビザ制度の中に隠されています。この記事では、サッカーファンなら知っておきたいプレミアリーグの外国人就労ビザの仕組みについて、ポイント制度から最新のルール変更まで、わかりやすく解説していきます。
プレミアリーグの外国人就労ビザとは?厳しい基準の基本

世界中からトッププレーヤーが集まるプレミアリーグですが、イングランド(イギリス)国外の選手がプレーするためには、サッカー選手としての実力だけでなく、イギリス政府が定める「就労ビザ」を取得する必要があります。これは単なる手続きではなく、選手のこれまでのキャリアが厳しく評価される、まさに「プレミアリーグでプレーする資格があるか」を問う審査なのです。ここでは、その基本となる制度の概要と考え方について見ていきましょう。
なぜ就労ビザが必要なの?ブレグジットがもたらした変化
特に大きな転換点となったのが、イギリスのEU離脱、通称「ブレグジット」です。2021年以前、EU加盟国の国籍を持つ選手は「労働者の移動の自由」という原則により、就労ビザなしでイギリスのクラブと契約できました。 しかしブレグジットによってこの特例がなくなり、フランス、ドイツ、スペインといったサッカー強国の選手たちも、日本人選手やブラジル人選手などと同じように、厳格な就労ビザの取得が必須となったのです。
この変更は、プレミアリーグのクラブの補強戦略にも大きな影響を与えました。 これまでのように気軽にEUから若手選手を獲得することが難しくなり、すべての外国人選手が同じ基準で評価されることになったのです。 そのため、これから解説するGBEという制度の重要性が、以前にも増して高まっています。
GBE(Governing Body Endorsement)とは?
プレミアリーグで選手が就労ビザを申請するためには、まずイングランドサッカー協会(FA)から「GBE(Governing Body Endorsement)」という推薦状を取得する必要があります。 これはFAが「この選手は、イングランドのサッカー界に貢献できるレベルの、優れたプロサッカー選手である」とお墨付きを与える証明書のようなものです。
このGBEがなければ、就労ビザの申請に進むことすらできません。FAは、選手の実力を客観的に評価するために、独自のポイント制度を設けています。 選手の代表歴やクラブでの出場実績などを細かく数値化し、その合計点が基準に達しているかどうかでGBEを発行するかどうかを判断します。
つまり、プレミアリーグへの移籍は、クラブ間の合意や選手との契約だけでは完結しません。FAが定めるGBEの基準をクリアするという、もう一つの大きなハードルを越える必要があるのです。このGBE制度こそが、プレミアリーグの外国人選手獲得における最も重要な仕組みと言えるでしょう。
自動発行基準(Auto Pass)の仕組み
GBEを取得する方法として、最も確実で分かりやすいのが「自動発行基準(Auto Pass)」を満たすことです。 これは、選手の代表チームでの実績が特に優れている場合に、複雑なポイント計算をせずとも自動的にGBEが発行されるというものです。
具体的には、選手の国籍(代表チーム)のFIFAランキングと、その代表チームでの公式戦出場率によって決まります。 FIFAランキングが高い国の代表選手ほど、求められる出場率は低く設定されています。
| FIFAランキング | 求められるA代表での公式戦出場率(過去24ヶ月) |
|---|---|
| 1位~10位 | 30%以上 |
| 11位~20位 | 45%以上 |
| 21位~30位 | 60%以上 |
| 31位~50位 | 75%以上 |
*21歳以下の選手の場合は、過去12ヶ月が審査対象期間となります。
例えば、FIFAランキング上位のブラジル代表やフランス代表の選手であれば、直近2年間の公式戦のうち3割以上に出場していれば、この基準をクリアできます。日本代表は20位前後になることが多いため、約60%以上の出場率が求められることになります。 A代表のレギュラークラスの選手であれば、この自動発行基準によってスムーズに移籍が実現する可能性が高いと言えるでしょう。
就労ビザ取得のポイント制(GBE)を詳しく解説

自動発行基準を満たせない場合、選手はポイント制でGBE取得を目指すことになります。FAは6つの項目(テーブル)を設けており、選手の様々な実績を点数化します。 この合計点が15ポイント以上に達すれば、GBEが発行される仕組みです。 ここでは、その評価項目を一つずつ見ていきましょう。
国際Aマッチへの出場実績
自動発行基準と同様に、代表チームでの活動は非常に重要な評価項目です。 こちらは出場率に応じて、細かくポイントが設定されています。国のFIFAランキングが高いほど、少ない出場率でも高いポイントが得られるように傾斜がつけられています。
例えば、FIFAランキング21~30位の国の選手(日本代表が該当する場合が多い)の場合、出場率が50~59%であれば10ポイント、40~49%であれば9ポイントといったように、段階的にポイントが付与されます。 代表に選ばれてはいるものの、レギュラーとして定着していない選手でも、ここでポイントを稼ぐことが可能です。ただし、親善試合は原則として対象外となるなど、試合の種類にも規定があります。
所属クラブでのプレー時間
次に重視されるのが、所属クラブの国内リーグ戦での出場時間です。 シーズンを通して、どれだけチームの主力としてプレーしていたかが評価されます。具体的には、所属クラブがそのシーズンに行った国内リーグの総試合時間のうち、選手が何パーセント出場したかに応じてポイントが与えられます。
この項目でも、所属リーグのレベルが大きく関わってきます。後述する「リーグのクオリティ」で高い評価(Band1やBand2)を受けているリーグに所属している選手は、同じ出場率でもより多くのポイントを獲得できます。例えば、スペインのラ・リーガで出場率90%以上の選手と、Jリーグで出場率90%以上の選手では、前者の方が格段に高いポイントを得られる仕組みになっています。
所属クラブのリーグレベルと成績
選手の所属クラブが、国内リーグでどのような成績を収めたかも評価対象です。 前シーズンの最終順位に応じてポイントが加算されます。もちろん、これもリーグのレベルによって得られるポイントが異なります。
例えば、プレミアリーグやラ・リーガといった最高レベル(Band1)のリーグで優勝したクラブに所属していた選手には、高いポイントが与えられます。 一方で、それよりも下のバンドに位置付けられているリーグの場合、同じ優勝でも獲得できるポイントは少なくなります。 また、リーグ戦で全く試合に出場(ベンチ入り)していない場合は、たとえチームが優勝してもこの項目のポイントは得られません。
所属クラブの大陸大会での成績
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)やヨーロッパリーグ(EL)、南米のコパ・リベルタドーレス、アジアのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)といった、各大陸のクラブ選手権での成績もポイントになります。
評価は2つの側面から行われます。
- クラブが大会のどのステージまで勝ち進んだか
- 選手自身がその大会でどれだけの時間プレーしたか
当然ながら、最もレベルが高いとされるUEFAチャンピオンズリーグでの実績は高く評価されます。 例えば、CLで決勝トーナメントに進出し、かつ選手自身も多くの試合に出場していれば、かなりの高ポイントが期待できます。 JリーグのクラブがACLに出場した場合もポイント対象となりますが、大会のレベル評価(Band)がCLより低いため、得られるポイントは限定的になります。
所属リーグのクオリティ
ここまでの項目で何度も触れてきましたが、選手が現在所属している、あるいは直近まで所属していたリーグ自体のレベル(質)も、独立した評価項目としてポイントが付与されます。 FAは世界中のリーグを「Band(バンド)」という6段階のカテゴリーに分類しています。
| バンド | 主なリーグの例 |
|---|---|
| Band 1 | プレミアリーグ(イングランド)、ラ・リーガ(スペイン)、ブンデスリーガ(ドイツ)、セリエA(イタリア)、リーグ・アン(フランス) |
| Band 2 | プリメイラ・リーガ(ポルトガル)、エールディヴィジ(オランダ)、ベルギー・プロ・リーグ、トルコ・シュペル・リガなど |
| Band 3 | チャンピオンシップ(イングランド2部)、スイス・スーパーリーグなど |
| Band 4 | メジャーリーグサッカー(アメリカ)、アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンなど |
| Band 5 | J1リーグ(日本)、Kリーグ1(韓国)など |
| Band 6 | 上記以外のリーグ |
*リーグのバンドは定期的に見直されます。
かつてJリーグは最も低いBand6でしたが、2023年のルール改定によりBand5に引き上げられました。 これにより、Jリーグでプレーする選手が以前よりもポイントを獲得しやすくなり、プレミアリーグへの移籍の可能性が少し広がったと言えます。
ポイントが足りなくても移籍できる?例外規定(ESC)とは

自動発行基準を満たさず、ポイント計算でも15ポイントに届かなかった場合、プレミアリーグへの道は完全に閉ざされてしまうのでしょうか。実は、そうではありません。「例外的な才能を持つ選手」を救済するための特別な審査プロセスが存在します。それが「ESC(Exceptions Panel)」と呼ばれる例外規定です。
ESC(Exceptions Panel)の役割
ESC(Exceptions Panel)は、ポイントという数字だけでは測れない選手の才能や将来性を評価し、GBEの発行を個別に審査するための専門家委員会です。 ポイントが10~14点だった選手が、このパネルによる審査の対象となります。
三笘薫選手がブライトンへ移籍した際も、Jリーグからの直接移籍ではポイントが足りなかったため、一度ベルギーのユニオン・サン=ジロワーズへレンタル移籍し、そこで実績を積みました。 もし、このESCのような制度がなければ、多くの才能ある若手選手がプレミアリーグでプレーするチャンスを失ってしまう可能性があるため、非常に重要な役割を担っていると言えます。
ESCが考慮する特別な事情とは?
ESCの審査では、ポイント制の項目だけでは評価しきれない、様々な「特別な事情」が考慮されます。委員会が特に注目するのは、以下のような点です。
- 将来性のある若手選手か
ユース代表での華々しい経歴や、同年代の選手の中で突出した才能を持っていると客観的に判断される場合、高く評価されることがあります。 - 怪我などにより、やむを得ず代表戦やクラブの試合に出場できなかったか
本来であれば代表チームの常連である選手が、長期の怪我によって出場機会を失い、ポイントが不足してしまった場合などは、その事情が酌量されることがあります。 - 移籍しようとしているクラブにとって、本当に必要な選手であるか
クラブがなぜその選手を熱望しているのか、チームの戦術にどうフィットするのかといった、クラブ側からの具体的な推薦理由も重要な判断材料となります。 - その他の客観的な評価
移籍金の額や年俸も、選手の市場価値を示す指標として考慮される場合があります。
これらの要素を総合的に検討し、委員会が「GBEを発行するに値する」と判断すれば、ポイント不足の選手でもプレミアリーグへの移籍が認められるのです。
ESCによって移籍が実現した選手の事例
この例外規定(ESC)は、実際に多くの選手のプレミアリーグ移籍を後押ししてきました。特に、まだA代表での実績が少ないながらも、欧州のクラブがその才能を高く評価した若手有望株の獲得において、この制度が活用されるケースが多く見られます。
例えば、ブラジルやアルゼンチンといった南米のリーグで頭角を現した10代の選手が、ビッグクラブへ移籍する際には、A代表歴がまだないためにポイントが不足することがよくあります。しかし、クラブがその選手の傑出した才能をESCで証明することにより、移籍が実現するのです。
日本人選手においても、冨安健洋選手がボローニャ(セリエA)からアーセナルへ移籍した際など、セリエAでの高い評価がポイントを補い、移籍につながったと考えられます。 このように、ESCは厳格なポイント制度に柔軟性をもたらし、世界中の多様な才能をプレミアリーグに呼び込むための重要な仕組みとなっています。
2023年夏のルール変更点と今後の影響

プレミアリーグの就労ビザ制度は、常にイングランドサッカー界の状況に合わせて見直しが行われています。特に2023年6月には、今後の移籍市場に大きな影響を与える可能性のある重要なルール変更が発表されました。 この変更は、クラブがより柔軟に選手を獲得できるようになることを目的としています。
新たに導入された「指定外国人枠(BES)」
2023年のルール変更で最も注目すべきなのが、「BES(Bespoke Elite Significant)」とも呼ばれる、実質的な「指定外国人枠」の導入です。 これは、従来のGBE基準(ポイント制など)を満たさない選手であっても、各クラブが一定数獲得できるようになったという画期的な変更です。
これまで、どんなに才能のある選手でもGBE基準をクリアできなければ契約は不可能でした。しかし新ルールでは、プレミアリーグのクラブは最大4人まで、この新しい枠を使って選手を獲得できるようになりました。
ただし、すべてのクラブが一律で4人の枠を持てるわけではありません。各クラブに与えられる枠の数は、そのクラブが過去のシーズンでイングランド人選手をどれだけ試合に出場させたかによって変動します。 イングランド人選手の育成に貢献しているクラブほど、多くの枠が与えられる仕組みになっており、国内選手の出場機会確保とのバランスが図られています。
若手有望株の獲得が容易に?
この「指定外国人枠」の導入によって、各クラブはこれまで獲得が難しかったタイプの選手にアプローチしやすくなりました。特に大きな影響を受けるのが、若手の有望株です。
南米やアフリカなど、欧州以外の地域には、まだA代表での実績はほとんどないものの、計り知れないポテンシャルを秘めた10代の選手が数多く存在します。従来のポイント制度では、彼らがGBE基準を満たすことはほぼ不可能でした。しかし、この新しい枠を使えば、クラブは将来性を見込んでこうした「原石」を獲得し、自クラブで育成していくことが可能になります。
これにより、プレミアリーグのクラブ間の若手選手獲得競争は、よりグローバルで激しいものになることが予想されます。ファンにとっては、将来のスター候補が早い段階でプレミアリーグにやってくるのを見る機会が増えるかもしれません。
Jリーグからの移籍への影響
このルール変更は、Jリーグでプレーする選手、特に若手選手にとって追い風となる可能性があります。前述の通り、2023年の変更ではJリーグのリーグレベル評価(バンド)がBand6からBand5へと引き上げられました。 これだけでも、Jリーグでの活躍が以前よりポイントに結びつきやすくなっています。
それに加え、この「指定外国人枠」ができたことで、たとえポイントが基準に満たなくても、プレミアリーグのクラブが「この選手には特別な才能がある」と判断すれば、獲得に乗り出す道が開かれました。三笘薫選手や遠藤航選手の活躍により、プレミアリーグのクラブの日本人選手、ひいてはJリーグに対する注目度は高まっています。
もちろん、この枠を使って誰を獲得するかはクラブの戦略次第であり、競争は非常に厳しいものです。しかし、Jリーグからプレミアリーグへの直接移籍というルートが、これまで以上に現実的な選択肢になったことは間違いないでしょう。
まとめ:プレミアリーグの外国人就労ビザ制度を理解して、もっとサッカーを楽しもう

この記事では、プレミアリーグでプレーするために外国人選手が乗り越えなければならない就労ビザの複雑な制度について解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返ってみましょう。
- ブレグジットの影響は大きい:2021年以降、EU国籍の選手も他の外国人選手と同様に、厳しい就労ビザの取得が必須となりました。
- GBEがお墨付き:移籍の前提として、FA(イングランドサッカー協会)からGBE(統括団体の推薦)を得る必要があります。
- 評価はポイント制が基本:代表での出場歴、クラブでの出場時間や成績、所属リーグのレベルなどが細かく点数化され、合計15ポイント以上で基準クリアとなります。
- 救済措置も存在する:ポイントが足りなくても、専門家委員会(ESC)が才能を認めれば移籍が可能な「例外規定」があります。
- 2023年の新ルール:GBE基準を満たさない選手でも獲得できる「指定外国人枠」が導入され、クラブは最大4人まで選手を獲得できるようになりました。
この就労ビザ制度は、一見すると単なる事務手続きのように思えるかもしれません。しかし、その背景には自国の選手を育成したいというイングランドサッカー協会の想いや、世界中から最高レベルの選手を集めてリーグの魅力を高めたいという思惑が複雑に絡み合っています。
この仕組みを少し知るだけで、夏の移籍市場のニュースがこれまでとは違って見えてくるはずです。「なぜあの若手選手はすぐにレンタルされるのか?」「この移籍はビザの問題をクリアできるのか?」といった視点を持つことで、プレミアリーグをより深く、多角的に楽しむことができるでしょう。