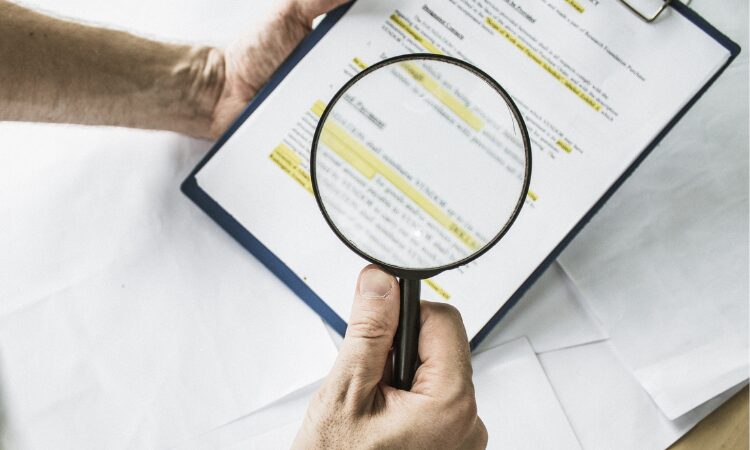サッカーの試合を見ていると、「S級ライセンス」という言葉を耳にすることがありませんか?これは、Jリーグのクラブや日本代表の監督を務めるために必須となる、日本国内で最高峰の指導者資格のことです。
多くの元有名選手たちがこの資格を取得し、指導者として新たなキャリアをスタートさせています。この記事では、「サッカーのS級ライセンス保持者にはどんな人がいるの?」「そもそもS級ライセンスって何?」という疑問をお持ちの方のために、S級ライセンスの基本情報から、具体的な保持者の一覧、さらにはその非常に厳しい取得方法や難易度、驚きの費用まで、分かりやすく解説していきます。
この記事を読めば、監督たちの経歴や凄さがより深く理解でき、サッカー観戦がもっと面白くなること間違いなしです!
サッカーのS級ライセンス保持者一覧と資格の概要

Jリーグや日本代表の監督という、サッカー指導者のトップに立つために不可欠なS級ライセンス。まずは、この資格がどのようなものなのか、そして近年どのような指導者たちがこの栄誉ある資格を手にしているのかを見ていきましょう。
S級ライセンスとは?国内最高峰の指導者資格
サッカーの指導者ライセンスは、キッズリーダーから始まり、D級、C級、B級、A級ジェネラル、そしてS級というピラミッド構造になっています。
- C級・D級: 主に子どもたちへの指導や、アマチュアチームの指導の基礎を学びます。
- B級: 高校生年代以下の監督や、より高いレベルのアマチュアチームの指導が可能になります。
- A級ジェネラル: Jリーグクラブのコーチや、JFL(日本フットボールリーグ)などアマチュアトップチームの監督を務めることができます。
そして、これら全てのステップの頂点に立つのがS級ライセンスです。プロの選手を指導し、チームを勝利に導くための高度な戦術知識、マネジメント能力、人間性など、指導者に求められるあらゆる能力を兼ね備えている証明となります。
JFAが公表している近年のS級ライセンス取得者一覧
日本サッカー協会(JFA)は、毎年のS級コーチ養成講習会を修了し、理事会で承認されたS級ライセンス認定者を公式サイトで発表しています。 ここでは、近年どのような指導者たちが新たにS級ライセンスを取得したのか、特に注目度の高い元選手を中心に見ていきましょう。
2023年度 S級ライセンス取得者(一部抜粋) 2023年度は、元日本代表のレジェンドである中村憲剛さんがS級ライセンスを取得したことが大きな話題となりました。
| 氏名 | 主な経歴(選手時代) | 備考 |
|---|---|---|
| 中村 憲剛 | 元日本代表、川崎フロンターレ一筋で活躍 | 川崎フロンターレFRO、U-17日本代表ロールモデルコーチなどを歴任 |
2024年度 S級ライセンス取得者(一部抜粋) 2024年5月には、元日本代表FWの大黒将志さんや北嶋秀朗さん、浦和レッズで長年活躍した平川忠亮さんなど、多くの元JリーガーがS級ライセンスを取得しました。
| 氏名 | 主な経歴(選手時代) | 現在の主な役職(2024年5月時点) |
|---|---|---|
| 大黒 将志 | 元日本代表、ガンバ大阪などで活躍 | ティアモ枚方コーチ |
| 北嶋 秀朗 | 元日本代表、柏レイソルなどで活躍 | クリアソン新宿監督 |
| 平川 忠亮 | 元浦和レッズ | 浦和レッズユース監督 |
2024年度 S級コーチ養成講習会 受講者(一部抜粋) 未来のJリーグ監督を目指し、2024年度の講習会には、中村俊輔さんや阿部勇樹さんといった、サッカーファンなら誰もが知る名選手たちが参加しています。 彼らがライセンスを取得し、監督としてピッチに戻ってくる日が待たれます。
| 氏名 | 主な経歴(選手時代) | トライアル申込時の役職 |
|---|---|---|
| 中村 俊輔 | 元日本代表、セルティック(スコットランド)などで活躍 | 横浜FCコーチ |
| 阿部 勇樹 | 元日本代表、浦和レッズなどで活躍 | 浦和レッズユースコーチ |
| 林 陵平 | 東京ヴェルディなどで活躍 | 東京大学監督 |
なぜ全指導者の一覧は公表されていないのか?
「S級ライセンスを持っている人全員のリストはないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。しかし、JFAの公式サイトで公表されているのは、基本的に各年度の新規認定者の情報です。 全保持者の網羅的なリストが一般に公開されていないのには、いくつかの理由が考えられます。
一つは個人情報保護の観点です。ライセンス情報は個人の資格情報にあたるため、本人の同意なく全てを公開することは難しいでしょう。
また、S級ライセンスは一度取得すれば永久に有効というわけではなく、定期的な研修(リフレッシュ研修)への参加が義務付けられています。 最新の指導理論を学び続けることでライセンスは更新されますが、もし研修を受けなければ資格が失効する可能性もあります。そのため、常に変動する可能性のある全保持者リストを正確に維持・公開するのは現実的ではないという側面もあります。
S級ライセンスで何ができる?監督になるための必須資格

国内最高峰の指導者資格であるS級ライセンス。この資格を手にすることで、指導者としてのキャリアは大きく開かれます。具体的にどのようなチームを率いることが可能になるのか、その権威と役割について詳しく見ていきましょう。
Jリーグクラブの監督になれる
S級ライセンスが持つ最も代表的な権限は、Jリーグクラブ(J1・J2・J3)の監督に就任できることです。 Jリーグの規約では、クラブの監督はS級ライセンス保持者でなければならないと定められており、これはリーグ全体のレベルと質を担保するための重要なルールです。
つまり、Jリーグで監督としてチームの指揮を執り、優勝を目指すためには、このS級ライセンスの取得が絶対的な条件となるのです。
日本代表の監督も務められる
S級ライセンスは、Jリーグクラブだけでなく、サッカー日本代表(男子・女子のA代表、各年代別代表)の監督を務めるためにも必要な資格です。 日本サッカーの象徴である代表チームを率いる指導者には、国内最高の指導者資格が求められるのは当然と言えるでしょう。
現在の日本代表監督である森保一監督も、もちろんS級ライセンス保持者です。サンフレッチェ広島で監督としてJ1を3度制覇した実績を持ち、S級ライセンスにふさわしい経歴を積んできました。将来、中村憲剛さんや中村俊輔さんのような元日本代表の名選手たちが、監督として日本代表を率いる姿を見られるかもしれません。
海外クラブでの指導も可能に
JFAのS級ライセンスは、AFC(アジアサッカー連盟)の最上位ライセンスである「AFC Pro-Diploma」と相互に認められています。 これにより、S級ライセンス保持者は、AFCに加盟している他の国や地域のプロリーグで監督を務めることが可能になります。
例えば、タイやオーストラリア、中東諸国のクラブチームで日本人指導者が監督として活躍できるのは、この制度があるからです。
ただし、UEFA(欧州サッカー連盟)のライセンスとの互換性はないため、S級ライセンスを持っていてもヨーロッパの主要リーグで監督を務めることはできません。 ヨーロッパで監督を目指す場合は、別途UEFAのライセンスを取得する必要があります。 とはいえ、アジア全域でプロクラブの監督ができるという点は、S級ライセンスが持つ大きな価値の一つです。
S級ライセンスの取得方法と道のり

Jリーグや日本代表の監督になるための必須資格、S級ライセンス。その取得への道のりは、非常に長く険しいものです。一体どのようなステップを経て、選ばれた指導者だけが手にすることができるのでしょうか。ここでは、その具体的な取得プロセスを詳しく解説します。
受講資格:B級・A級ジェネラルライセンスからのステップアップ
S級ライセンスは、誰でもいきなり挑戦できるわけではありません。まず、指導者ライセンスの階段を一段ずつ登っていく必要があります。
- C級・B級ライセンスの取得: 指導者としてのキャリアは、多くの場合C級ライセンスからスタートします。その後、B級ライセンスを取得し、アマチュアレベルでの指導経験を積みます。
- A級ジェネラルライセンスの取得: 次に、さらに難易度の高いA級ジェネラルライセンスに挑戦します。この資格を取得することで、Jリーグクラブのコーチなどを務めることが可能になります。
- 1年以上の指導実績: A級ジェネラルライセンスを取得した後、最低でも1年以上の指導経験を積むことが、S級への挑戦権を得るための条件となります。
- S級コーチ養成講習会トライアルへの合格: 上記の条件を満たした上で、年に一度実施される「S級コーチ養成講習会トライアル」を受験し、合格しなければなりません。 このトライアルでは、指導実践や面談などを通じて、S級の講習会に参加するにふさわしい能力と資質があるかが厳しく審査されます。
このように、S級の講習会に参加するだけでも、長年の指導経験と狭き門であるトライアルの突破が必要不可欠なのです。
講習会の内容と期間:国内外での長期研修
S級コーチ養成講習会は、約8ヶ月から1年近くにも及ぶ長期間のプログラムです。 受講者はその間、指導の仕事と両立させながら、非常に密度の濃いカリキュラムに取り組むことになります。
講習会の内容は多岐にわたりますが、主に以下のようなモジュールで構成されています。
- 国内での集合研修: 定期的に数日間の合宿形式で行われ、最新の戦術理論、トレーニング理論、スポーツ科学、心理学、チームマネジメントなどを学びます。 講義だけでなく、指導実践やディスカッションも頻繁に行われます。
- Jクラブでの実地研修: Jリーグのクラブに帯同し、プロの現場での指導方法やクラブ運営を学びます。
- 海外プロクラブでの実地研修(インターンシップ): 講習会のハイライトとも言えるのが、海外のプロクラブでの研修です。 実際にヨーロッパなどの先進的なクラブへ赴き、トップレベルの指導や育成システムを肌で感じる貴重な機会となります。この海外研修は必須とされています。
これらの研修を通じて、座学だけでは得られない実践的なスキルと国際的な視野を養っていきます。
指導実践や論文などの厳しい審査
講習会の全カリキュラムをただこなすだけでは、ライセンスは認定されません。最終的には、厳しい審査に合格する必要があります。
審査項目には、以下のようなものがあります。
- 筆記試験: 学んできた理論に関する知識が問われます。
- 指導実践試験: 実際に選手たちを指導し、その指導力やコミュニケーション能力、問題解決能力が評価されます。
- 口頭試験: 指導者としての哲学や考え方、プレゼンテーション能力などが問われます。
- 研修レポート・論文の提出: 海外研修などで学んだことをまとめ、自身の指導理論を構築する能力が審査されます。
これらの全ての評価項目で合格基準を満たした者だけが、最終的に日本サッカー協会(JFA)の理事会で承認され、晴れてS級ライセンス保持者として認定されるのです。
S級ライセンス取得の難易度と費用

指導者としての最高峰を目指すS級ライセンス。その取得が極めて困難であることは想像に難くありませんが、具体的にどれほどの難易度で、どれくらいの費用が必要になるのでしょうか。ここでは、その厳しい現実について詳しく見ていきます。
合格率はどのくらい?超難関と言われる理由
S級コーチ養成講習会の明確な合格率は公表されていませんが、非常に低いと言われています。 そもそも、講習会に参加できる受講者自体が、厳しいトライアルを勝ち抜いたエリートたちです。2023年度の定員は16〜20名、2024年度は20名と、毎年全国でわずか20人程度しか受講のチャンスを得られません。
超難関と言われる理由は、単に受講者数が少ないからだけではありません。長期間にわたる講習会では、サッカーに関するあらゆる知識とスキルが問われます。戦術眼はもちろんのこと、選手をまとめ上げるマネジメント能力、メディア対応、クラブ経営に関する知識まで求められ、一つでも基準に達しなければ合格はできません。元日本代表選手であっても、簡単に取得できる資格ではないのです。
受講にかかる費用は?
S級ライセンス取得には、莫大な費用も必要となります。2025年度の開催要項によると、講習会の受講料だけで550,000円(税込)です。
しかし、実際に必要となる費用はこれだけではありません。
- 交通費・宿泊費: 講習会は国内各地で数日間の合宿形式で行われることが多く、その都度、会場までの交通費や宿泊費が自己負担となります。
- 海外研修費: カリキュラムに必須で含まれている海外プロクラブへのインターンシップにかかる渡航費や滞在費も、基本的には自己負担です。
これらの費用を合計すると、総額で200万円以上、場合によっては300万円を超えるとも言われています。 Jリーグクラブに所属している指導者はクラブから補助を受けられる場合もありますが、そうでない指導者にとっては非常に大きな経済的負担となります。
保持し続けるためのリフレッシュ研修
S級ライセンスは、一度取得すれば終わりではありません。その価値を維持し続けるためには、定期的にリフレッシュ研修会などに参加し、ポイントを獲得してライセンスを更新する必要があります。
これは、サッカーの戦術やトレーニング方法が日々進化していく中で、指導者も常に最新の知識を学び、アップデートし続けることが重要だからです。リフレッシュ研修を通じて、指導者同士で情報を交換したり、新たな知見を得たりすることで、自身の指導レベルをさらに高めていくことが求められます。
このように、S級ライセンスは取得するまでも、そして保持し続けるためにも、多大な努力と投資が必要な、まさに指導者の最高峰の証なのです。
有名なS級ライセンス保持者たち

S級ライセンスという狭き門を突破した指導者の中には、私たちがよく知る元スター選手たちが数多くいます。選手としてピッチを沸かせた彼らが、今度は監督としてどのようなサッカーを見せてくれるのか。ここでは、様々なカテゴリーで活躍する有名なS級ライセンス保持者を紹介します。
元日本代表選手から監督になった指導者
選手としてワールドカップや海外リーグで輝かしい実績を残した元日本代表選手たちが、指導者としてもトップレベルを目指し、S級ライセンスを取得しています。
- 森保 一(もりやす はじめ) 現サッカー日本代表監督。現役時代は「ボランチ」というポジションを日本に定着させた名選手の一人です。指導者としては、サンフレッチェ広島の監督として3度のJ1リーグ優勝を成し遂げた輝かしい実績を持っています。
- 中村 憲剛(なかむら けんご) 2023年度にS級ライセンスを取得。 川崎フロンターレのレジェンドとして知られ、卓越したテクニックと戦術眼で長年チームを牽引しました。引退後は解説者や育成年代の指導に携わり、満を持してのS級取得となりました。今後の監督就任が非常に期待されています。
- 内田 篤人(うちだ あつと) シャルケ04(ドイツ)で活躍した元日本代表サイドバック。引退後、若くしてS級ライセンス取得の道に進み、現在は日本代表のロールモデルコーチや解説者として活躍しています。
- 大黒 将志(おおぐろ まさし) 「大黒様」の愛称で親しまれた元日本代表ストライカー。2005年のワールドカップ予選、北朝鮮戦での劇的なゴールは語り草です。2024年にS級ライセンスを取得し、指導者としての新たな一歩を踏み出しました。
2024年度のS級講習会には中村俊輔さんや阿部勇樹さんが、2025年度には槙野智章さんや市川大祐さんが参加しており、今後も多くの元スター選手がS級ライセンスを取得していくことが予想されます。
Jリーグで活躍する現役監督
もちろん、Jリーグの各クラブを率いる監督たちの多くも、S級ライセンスを持つ優れた指導者です。元Jリーガーだけでなく、高校サッカーの指導者からキャリアを積み上げてきた監督や、海外での指導経験が豊富な監督など、その経歴は様々です。試合を見る際には、対戦する両チームの監督がどのような経歴を持ち、どんなサッカーを目指しているのかを調べてみると、より一層観戦が楽しくなるでしょう。
女性のS級ライセンス保持者
女子サッカー界でも、S級ライセンスを取得してトップレベルで活躍する指導者が増えています。
- 高倉 麻子(たかくら あさこ) 元なでしこジャパン(日本女子代表)監督。女性指導者として先駆的な存在であり、長年女子サッカーの発展に貢献してきました。
- 本田 美登里(ほんだ みどり) WEリーグ(女子プロサッカーリーグ)のAC長野パルセイロ・レディースなどで監督を歴任。 静岡県出身で、半田悦子さんとともに「静岡三国決戦」と称された時代の名選手です。
近年、JFAは女性指導者の育成に力を入れており、WEリーグの監督を対象とした「A-Proライセンス」という資格を新設しました。 このライセンスを取得し、さらにコンバージョンコースを修了することでS級ライセンスへ移行できる道も開かれており、今後さらに女性のS級ライセンス保持者が増えていくことが期待されています。
まとめ:サッカーS級ライセンス保持者一覧を理解し、サッカー観戦をより深く楽しもう

この記事では、サッカーのS級ライセンスについて、その概要から保持者の一覧、そして取得の難しさまでを詳しく解説してきました。
S級ライセンスが、いかに特別な資格であるかがお分かりいただけたかと思います。監督たちがどのような厳しい道のりを経てその場所に立っているのかを知ることで、彼らの戦術や采配の一つひとつが、より深い意味を持って見えてくるはずです。
次にサッカーを観戦する際には、ぜひ監督の経歴にも注目してみてください。S級ライセンスという視点を持つことで、あなたのサッカーライフがさらに豊かで楽しいものになることを願っています。