サッカーの試合中、選手たちがどれだけ走っているか考えたことはありますか?テレビ中継などで「〇〇選手の走行距離は12km」といった情報を見かける機会が増え、選手の運動量を評価する指標として「走行距離」が注目されています。
プロのサッカー選手は、90分間の試合でフルマラソン(42.195km)の約4分の1にあたる10km以上もの距離を走ることがあります。 この驚異的な運動量は、彼らの体力やチームへの貢献度を測る上で非常に重要なデータです。 この記事では、サッカー選手の平均走行距離から、ポジションによる違い、国内外のトッププレーヤーの記録、そして走行距離が試合に与える影響まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。走行距離という視点を持つことで、サッカー観戦がより一層面白くなること間違いなしです。
サッカー選手の走行距離とは?基礎知識をわかりやすく解説

サッカー選手のパフォーマンスを語る上で欠かせない指標の一つが「走行距離」です。この数値は選手の運動量や貢献度を客観的に示すものとして、近年多くのメディアで取り上げられています。まずは、走行距離に関する基本的な知識を深めていきましょう。
1試合の平均走行距離はどれくらい?
プロのサッカー選手は、1試合(90分間)で平均して約10kmから11kmの距離を走ると言われています。 もちろん、これはあくまで平均値であり、選手によっては12kmや13km以上走ることも珍しくありません。 Jリーグのデータを見ても、多くのチームが1試合のチーム合計走行距離で110kmを超えており、一人当たりに換算すると10kmを超える計算になります。
高校サッカーでも平均8〜9kmを走ると言われており、プロと大きな差がないことからも、サッカーがいかに過酷なスポーツであるかが分かります。 この走行距離には、ダッシュだけでなく、ジョギングや歩いている時間も含まれています。
ポジションによって走行距離は変わる?
サッカーは11人それぞれに与えられたポジションと役割が異なります。そのため、求められる動きも変わり、結果として走行距離にも差が生まれます。
| ポジション | 1試合あたりの平均走行距離 | 特徴 |
|---|---|---|
| ミッドフィールダー(MF) | 約11km 〜 13km | 攻守にわたってピッチの中央でプレーするため、最も走行距離が長くなる傾向がある。 |
| サイドバック(SB) / サイドハーフ(SH) | 約9km 〜 11km | サイドのライン際を攻撃と守備で何度もアップダウンするため、走行距離が多くなる。 |
| フォワード(FW) | 約9km 〜 11km | 相手のディフェンスラインとの駆け引きや、前線からの守備(プレス)など、戦術によって走行距離が大きく変動する。 |
| センターバック(CB) | 約7km 〜 9km | 主に自陣のゴール前でプレーすることが多く、フィールドプレーヤーの中では走行距離が比較的少なくなる傾向がある。 |
| ゴールキーパー(GK) | 約4km 〜 5km | 基本的にペナルティエリア内でのプレーが主だが、攻撃の起点となる動き出しや守備範囲の広さによっては7km以上走る選手もいる。 |
このように、最も走るポジションは、攻守の要となるミッドフィールダー(特にボランチ)です。 ピッチの広範囲をカバーし、常にボールに関わり続けるため、必然的に運動量が多くなります。
走行距離はどうやって計測しているの?
選手の走行距離は、スタジアムに設置された複数の高性能カメラで選手一人ひとりの動きを追跡する「トラッキングシステム」によって計測されるのが一般的です。 Jリーグでは2015年からこのシステムが導入されており、走行距離のほか、スプリント(時速24km以上での全力疾走)の回数などのデータも詳細に分析されています。
個人で走行距離を測りたい場合は、スパイクに埋め込むタイプの小型計測機器なども市販されており、スマートフォンアプリと連携して自分のプレーをデータで振り返ることも可能です。
走行距離が長い選手は誰?国内外のランキング
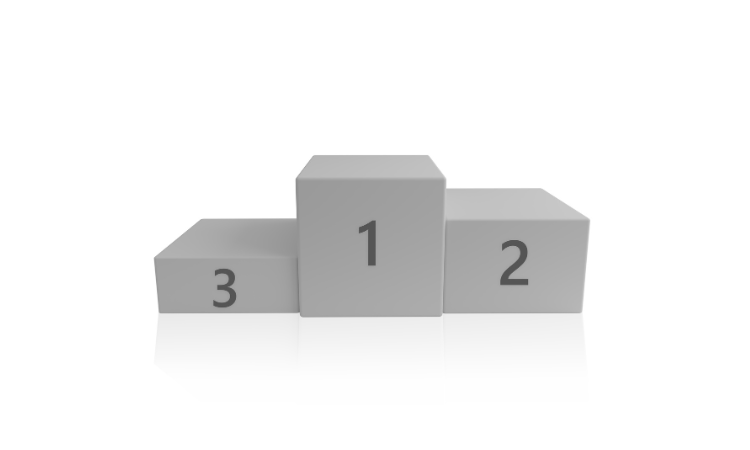
走行距離は、選手の献身性やスタミナを示す一つの指標です。ここでは、国内外のリーグや大会で、特に長い走行距離を記録している選手たちにスポットを当ててみましょう。
世界で走るトッププレーヤーたち
世界最高峰のリーグの一つであるイングランド・プレミアリーグでは、毎シーズン走行距離のランキングが発表されます。2023-24シーズンでは、ニューカッスル・ユナイテッドに所属するブラジル代表MFブルーノ・ギマランイス選手がシーズン合計で423kmを走り、トップに輝きました。 このように、ランキング上位にはチームの攻守を支えるミッドフィールダーの選手が多く名を連ねる傾向があります。
一方で、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手のように、走行距離は比較的少ないながらも決定的な仕事をするスーパースターも存在します。 メッシ選手の1試合平均走行距離は7〜8km程度で、ゴールキーパーより少ない試合もあるほどです。 これは、試合の大部分を歩いて体力を温存し、勝負どころで一気に加速するという、彼のプレースタイルとチーム戦術によるものです。
Jリーグのスタッツから見る走る選手
Jリーグでも公式サイトで走行距離のデータが公開されており、毎節どの選手が最も走ったかを確認することができます。 過去のデータを見ると、サガン鳥栖や横浜F・マリノスといった、前線から激しいプレスをかける戦術(ハイプレス)を採用するチームの選手が上位にランクインすることが多いです。
例えば、2022年シーズンには、当時横浜F・マリノスに所属していた西村拓真選手が1試合で14.12kmという驚異的な記録を残したこともあります。 このように、Jリーグでも1試合で12km以上を走る選手は珍しくなく、彼らのハードワークがチームの勝利に大きく貢献しています。
日本代表で最も走る選手は?
日本代表においても、走行距離は選手を評価する上で重要なデータとなっています。記憶に新しい2022年のカタールワールドカップでは、グループリーグ3試合の合計で鎌田大地選手がチームトップの31.83kmを記録しました。 さらに、スプリント回数や相手にプレッシャーをかけた回数でもチーム最多となっており、数字の上でも彼の攻守にわたる献身性が証明されています。
また、過去のワールドカップでは長友佑都選手も驚異的な運動量を見せています。2018年のロシアワールドカップでは、4試合の合計走行距離が43.59kmと、フルマラソンを超える距離を走破しました。 このように、日本代表の選手たちは世界を相手にしても遜色ない運動量で戦っているのです。
走行距離が試合に与える影響

走行距離は選手の運動量を測る分かりやすい指標ですが、「ただ走れば良い」というわけではありません。ここでは、走行距離が試合の勝敗や戦術にどのように関わってくるのかを、より深く掘り下げていきます。
走行距離が多い=良い選手?
走行距離が多いことは、チームへの貢献度やハードワークを評価する上で重要な要素ですが、必ずしも「走行距離が多い=良い選手」とは限りません。 サッカーは、いかに効率よくプレーするかが求められるスポーツでもあります。無駄な走りが多くては体力を消耗するだけで、肝心な場面で力を発揮できなくなってしまいます。
「スプリント回数」も重要な指標
走行距離と合わせて注目されるのが「スプリント回数」です。スプリントとは、時速24km以上での全力疾走のことを指します。 試合の勝敗を分ける決定的な場面は、このスプリントによって生まれることがほとんどです。
例えば、ディフェンスラインの裏へ抜け出す動きや、カウンター攻撃、相手の決定機を防ぐための必死の戻りなど、試合の流れを大きく左右するプレーにはスプリントが不可欠です。トップレベルの選手になると、1試合で30回から40回以上もスプリントを繰り返します。 そのため、単に長い距離を走れるだけでなく、何度も全力疾走を繰り返せる能力(間欠性回復力)が現代サッカーでは非常に重要視されています。
走行距離とチームの戦術の関係
チーム全体の走行距離は、そのチームがどのような戦術を採用しているかを読み解くヒントにもなります。
- ハイプレス戦術のチーム: 相手陣地の高い位置から積極的にプレッシャーをかけてボールを奪いに行くため、チーム全体の走行距離やスプリント回数が多くなる傾向があります。 Jリーグではサガン鳥栖や横浜F・マリノスがその代表例です。
- リトリート(引いて守る)戦術のチーム: 自陣の深い位置で守備ブロックを固めてスペースを消すため、相手を追い回す動きが少なくなり、走行距離は比較的少なくなる傾向があります。
このように、走行距離のデータを見ることで、「このチームは積極的に前からボールを奪いに行っているな」「このチームはしっかり守ってカウンターを狙っているな」といった、チームの戦術的な狙いを推測することができます。 走行距離は、必ずしも強さと直結するわけではありませんが、チームの戦い方を反映する鏡のような役割を果たしているのです。
走行距離を伸ばすためのトレーニング

サッカーの試合で90分間走り続けるためには、高い持久力が不可欠です。ここでは、走行距離を伸ばし、試合終盤でもパフォーマンスを落とさないためのトレーニング方法をいくつかご紹介します。
持久力を高める有酸素運動
サッカーにおける持久力の基礎となるのが「全身持久力」です。 これは、長時間運動を続けられる能力のことで、心肺機能を高めることで向上します。 この全身持久力を鍛えるのに効果的なのが、有酸素運動です。
インターバル走 全力の70%程度のスピードで走る「急走期」と、ジョギングなどの軽い運動でつなぐ「緩走期」を交互に繰り返すトレーニングです。 心拍数を意図的に上げ下げすることで、心肺機能に高い負荷をかけ、効率よく持久力を向上させることができます。
スプリント能力を上げる無酸素運動
走行距離だけでなく、試合を決めるスプリントを何度も繰り返すためには、「筋持久力」も重要です。 これは、筋肉が疲れずに力を出し続けられる能力のことで、無酸素運動によって鍛えられます。
ヒル・スプリント(坂道ダッシュ) 坂道を全力で駆け上がるトレーニングです。 平地でのダッシュよりも高い筋力が必要となり、下半身のパワーと持久力を同時に強化することができます。
効率的な走り方を身につける
ただ闇雲に走るだけでは、すぐに疲れてしまいます。走行距離を伸ばすためには、エネルギー消費の少ない効率的な走り方を身につけることも大切です。
- 正しいフォームを意識する: 体をまっすぐに保ち、やや前傾姿勢を意識します。 腕は肘を90度に曲げ、肩の力を抜いてリズミカルに振ることで、足の運びがスムーズになります。
- 足の着地点: 体の真下に近い位置で着地することを意識しましょう。 体から離れた位置でかかとから着地すると、ブレーキがかかってしまい、無駄なエネルギーを使ってしまいます。
- 地面を「押す」意識: 地面を強く「蹴る」のではなく、つま先で軽く「押す」イメージを持つと、地面からの反発力を効率よく推進力に変えることができます。
これらのトレーニングは、継続することで効果が現れます。 自分のレベルに合わせて、無理のない範囲で始めてみましょう。
まとめ:サッカーの走行距離を知って観戦をより楽しもう

この記事では、「走行距離」というキーワードを軸に、サッカー選手の驚異的な運動量から、ポジションによる違い、試合への影響、そして持久力を高めるトレーニング方法までを解説してきました。
プロサッカー選手が1試合で平均10km以上も走ること、そしてその距離がポジションやチームの戦術によって大きく変わることをご理解いただけたかと思います。 走行距離は単なる数字ではなく、選手の献身性やチームの戦術を読み解くための一つの指標です。
次にサッカーを観戦する機会があれば、ぜひ選手の走行距離やスプリント回数といったデータにも注目してみてください。「この選手は攻守にわたって走り回ってチームを助けているな」「このチームは走行距離は少ないけど、効率的なパスワークで試合を支配しているな」といった、これまでとは違った視点で試合を見ることができるはずです。走行距離の知識は、あなたのサッカー観戦をより深く、より面白いものにしてくれるでしょう。



